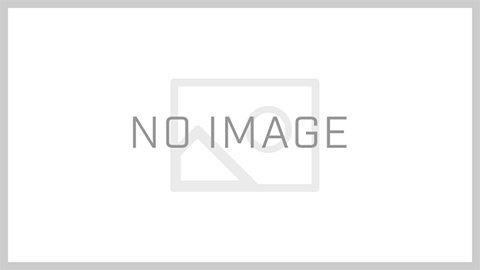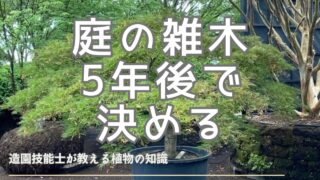尿素とは肥料の特徴とは?硫安との違いもわかりやすく紹介

肥料としてよく耳にする「尿素」ですが、実際にどんな成分が含まれていて、どのように使えばよいのか、いまいちわからないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、尿素とは肥料としてどんな特徴を持つのかをわかりやすく解説していきます。
まずは、尿素肥料成分とその効果について理解するところから始め、植物の成長にどのような影響を与えるのかを丁寧に解説します。次に、尿素はどんな時に使う?施用のタイミングを作物や季節ごとに具体的に紹介し、初心者でも安心して施肥できるような情報をお届けします。
また、植物に尿素をまくとどんな効果があるの?と疑問に感じている方に向けて、葉や茎の成長、病害虫への抵抗力など、尿素の持つ力についても詳しく触れていきます。そして最後に、よく比較される尿素と硫安のどちらを肥料にしたらいいですか?というテーマについて、両者の違いや使い分けのポイントを整理して解説します。
尿素の基本をしっかり押さえ、賢く使いこなせるようになるためのガイドとして、ぜひ参考にしてください。
-
尿素肥料の成分や植物への効果
-
尿素を使う適切なタイミングと施肥方法
-
尿素と硫安の違いと使い分け方
-
尿素施用時の注意点や失敗を防ぐコツ

尿素とは肥料としてどんな特徴がある?



尿素肥料成分とその効果について
尿素を肥料として使う前に、まずその成分と効果を正しく理解することが大切です。ここでは尿素に含まれる主な成分や、その成分が植物に与える具体的な効果について解説します。
尿素肥料の主成分は「窒素」
尿素肥料の最大の特徴は、約46%もの高濃度の窒素を含んでいることです。窒素は植物の生育に欠かせない三大栄養素の一つで、特に葉や茎の成長を促進します。尿素はその中でも最も窒素濃度が高い単肥であり、速効性もあるため、成長期の追肥などに適しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主成分 | 窒素(N)46%前後 |
| 分子式 | CO(NH₂)₂ |
| 外観 | 白色顆粒または結晶 |
| 性質 | 水に溶けやすく中性、無臭・無味 |
尿素の窒素が植物に与える影響
尿素の窒素は、植物の光合成を助け、葉の緑色(クロロフィル)を維持する役割を担います。そのため、葉が黄色くなっている植物や、元気のない株に施すと短期間で回復が見込めることがあります。また、茎の伸長や枝葉の分化を促進し、全体のバランス良い生育を支えることにもつながります。
利用の際の注意点とデメリット
ただし、尿素はその高い窒素濃度ゆえに、使い方を誤ると「肥料焼け」を引き起こす可能性があります。特に、若い苗や根が弱っている植物に対しては、使用量や濃度に十分な注意が必要です。また、過剰に使うと吸収されなかった窒素が土壌中に残り、地下水汚染や環境負荷の原因にもなります。
尿素はどんな時に使う?施用のタイミング

尿素肥料を効果的に使うには、「いつ」「どのような場面で」施用するのが適切なのかを把握しておくことが重要です。ここでは植物の生長段階や季節ごとの使い方について解説します。
成長初期や葉の色が薄い時期
植物の成長初期、特に葉が展開し始める時期には、窒素を多く必要とします。このタイミングで尿素を施すと、葉の色づきが良くなり、茎の伸びも期待できます。また、葉色が黄ばんでいたり、元気がないと感じたときも、尿素の散布が効果的です。
追肥としての活用
尿素は即効性が高いため、追肥として使うことが多くなります。例えば野菜や果樹では、収穫までに複数回の追肥を行いますが、その際に尿素を用いると、すぐに成長反応が出やすい傾向があります。
| 作物 | 推奨施用時期 | 用量(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| トマト | 開花期~果実肥大期 | 10g程度 |
| ミカン | 春芽の出る前/秋の収穫後 | 5~10g |
| 葉物野菜 | 生育中(20~30日間隔) | 5~15g |
季節ごとの使い方と注意点
尿素の肥効は土壌中の温度や水分量に左右されます。例えば、夏場は分解が早く2~3日で吸収される一方で、冬場は7日以上かかることもあります。雨の直前や灌漑の直後に施すと、尿素が流れてしまうため、天候を見て施用することが必要です。
アルカリ性の強い土壌ではアンモニアガスが揮発しやすいため、尿素の効果が下がることがあります。このような環境では、施肥から数日空けるか、別の肥料との併用が検討されます。
植物に尿素をまくとどんな効果があるの?
尿素を植物に施用すると、葉や茎の生育が活発になり、見た目にも元気な状態を保つことができます。ここでは、植物に尿素を与えることで期待できる主な効果と、施用時の注意点について解説します。
葉や茎の成長を強く促す
尿素に含まれる窒素成分は、植物の光合成を助けるクロロフィルの生成に関与しています。そのため、尿素を施すことで葉の緑色が濃くなり、健康的な姿へと導きます。特に葉が黄色くなっている植物や、成長が鈍っている株に対しては、数日で変化が見られることもあります。
根の発達を助ける間接的な効果
尿素は葉や茎の育成を直接的にサポートする肥料ですが、結果的にそれが根の発達にもつながります。葉がよく育つことで光合成が活発になり、植物全体にエネルギーが循環します。このプロセスが、根の伸長や養分吸収力の向上を助けます。
植物全体の抵抗力が高まる
栄養状態の良い植物は、病害虫への抵抗力も自然と高くなります。尿素で適切に窒素を補うことで、植物がストレスに強くなり、うどん粉病などの葉面疾患に対しても耐性が上がる傾向があります。ただし、病気を治す薬ではないため、予防的な効果にとどまる点は理解が必要です。
| 尿素の効果 | 対象部位 | 効果の現れ方 |
|---|---|---|
| クロロフィル増加 | 葉 | 緑が濃くなる・葉の黄変改善 |
| 成長促進 | 茎・枝 | 節間が伸びる・分枝が増える |
| 抵抗力向上 | 全体 | 病気にかかりにくくなる |
注意点:過剰施肥による障害に気をつける
尿素は吸収が早い分、使いすぎると肥料焼けや水質汚染の原因になります。特に若い苗や小さな鉢植えの場合、少量でも影響が出ることがあります。使用前には作物に合った濃度と量をしっかり確認しましょう。
尿素と硫安のどちらを肥料にしたらいいですか?

尿素と硫安(硫酸アンモニウム)は、どちらも窒素肥料として広く使われています。ここでは両者の違いや特徴を比較しながら、どんな場面でどちらを選べば良いのかを解説します。
成分と吸収スピードの違いを知っておく
尿素と硫安では、窒素の形や吸収のされ方に違いがあります。尿素は「尿素態窒素」、硫安は「アンモニア態窒素」を含んでおり、植物への吸収プロセスが異なります。
| 項目 | 尿素 | 硫安 |
|---|---|---|
| 窒素含有量 | 約46% | 約21% |
| 吸収形式 | 土壌で加水分解→アンモニア態 | 直接アンモニア態 |
| 速効性 | 高い(ただし若干の遅れあり) | 非常に高い |
| 土壌への影響 | 中性〜弱アルカリ性 | 酸性化しやすい |
| 葉面散布 | 可(適切な希釈が必要) | 不向き |
この表からも分かる通り、硫安は吸収が早く即効性がありますが、連用すると土壌が酸性に傾きやすいというデメリットがあります。一方、尿素は水に溶けやすく広い用途に対応できますが、正しい施用が求められます。
用途や目的に応じた選び方
例えば、酸性土壌を避けたい場合や葉面散布をしたい場合は尿素が適しています。逆に、速やかに窒素を効かせたい、短期間で効果を出したいといったケースでは硫安の方が向いています。
-
尿素を選ぶべき場面:葉面散布、果樹・園芸、アルカリ性との混合回避
-
硫安を選ぶべき場面:水田、酸性にしても問題のない土壌、すぐに効かせたい場合
尿素と硫安、それぞれの特性を理解した上で、適切な肥料を選ぶことが重要です。「ハイポネックスの肥料セット」は、各種肥料がバランスよく含まれており、用途に応じた使い分けが可能です。
最終的な判断は土壌や作物に応じて
どちらが優れているかは一概には言えません。あくまで土壌の性質、作物の種類、施肥目的によって適切な肥料を選ぶべきです。使用前には、pHや施肥履歴、作物の生育段階を確認することをおすすめします。
尿素とは肥料としてどう使えばいいのか?




野菜に使う際の注意点
尿素は野菜の成長を促進する優れた肥料ですが、使い方を間違えると逆効果になることがあります。ここでは、野菜栽培における尿素の正しい使い方と注意点を具体的に解説します。
濃度と施肥量に注意する
尿素は窒素含有量が非常に高いため、少量でも大きな効果があります。特に家庭菜園では、つい多めに施してしまうケースが多いですが、これは「肥料焼け」を招く原因となります。
| 野菜の種類 | 1㎡あたりの目安量 | 葉面散布濃度 |
|---|---|---|
| 葉物野菜(ほうれん草・小松菜) | 5~10g | 0.5~1.0% |
| 実野菜(ナス・ピーマン) | 10~15g | 0.5~1.0% |
| 根菜(ダイコン・ニンジン) | 5~10g | 基本は土壌施肥が中心 |
また、追肥として使う場合も、前回施用から20~30日以上の間隔をあけると過剰施肥を避けやすくなります。
土壌と混ぜ込む深さに工夫を
尿素は水に溶けやすく、土壌表面にまくと雨や灌漑で流されやすくなります。表面散布よりも、できるだけ土の中に10~15cm程度混ぜ込むと効果的です。また、混ぜたあとはすぐに灌水せず、数日経ってから水を与えるようにしましょう。
葉面散布では濃度と時期に注意
葉面散布は速効性がある一方で、濃度が高すぎると葉を傷める可能性があります。特に夏場の高温時や日差しの強い日中に散布すると、葉焼けのリスクが高まります。早朝または夕方に、濃度1%以下の希釈液を使うと安心です。
トマトへの活用ポイント

トマトは栄養を多く必要とする野菜であり、尿素のような窒素肥料が収量や果実の品質に大きく関わります。ただし、タイミングや量を誤ると、かえって病害や品質低下につながることもあります。
成長初期~果実肥大期に施すと効果的
トマトに尿素を使う場合、最も効果的なのは「開花期から果実肥大期」にかけてです。この時期は窒素を多く必要とするため、適量の尿素を施すことで茎葉の生育が促され、果実の肥大がスムーズになります。
| 生育ステージ | 推奨施用量(1㎡) | 備考 |
|---|---|---|
| 定植直後 | 5g程度 | 根に触れないように注意 |
| 開花期 | 10g程度 | 土壌または葉面散布で可 |
| 果実肥大期 | 10~15g | 葉の色を見ながら調整 |
尿素だけでなくリン酸やカリとの併用が効果的
トマトは窒素だけでなく、リン酸やカリウムもバランス良く必要とします。尿素を単独で使いすぎると、茎葉ばかりが繁り、花付きや果実品質が低下することがあります。そのため、複合肥料や有機肥料と組み合わせると、より効果的に栽培できます。
肥料のタイミングと果実の着色に注意
トマトの収穫が近づく時期に尿素を多く施すと、果実の着色が遅れたり、糖度が下がったりすることがあります。追肥は果実が色づく少し前までに済ませ、以降は控えるのが理想的です。また、尿素を葉面散布する際も、6月中旬以降は特に注意が必要です。
葉面散布のやり方と濃度
尿素は水に溶けやすく、葉からも吸収されやすいため「葉面散布」という方法で使われることが多くあります。この章では、尿素を葉から効率的に吸収させるための適切な濃度や散布方法についてご紹介します。
散布前に知っておきたい適正濃度
尿素を葉面散布に使う場合、濃度が高すぎると葉が焼けてしまう恐れがあります。作物の種類に応じた濃度を守ることで、安全かつ効果的な施用が可能です。
| 作物の種類 | 散布濃度の目安 | 散布の頻度 |
|---|---|---|
| 米・小麦・トウモロコシ | 1〜2% | 生育中に1〜2回 |
| 野菜(キャベツ・ほうれん草など) | 0.5〜1% | 20日間隔で1〜2回 |
| 果樹(ミカン・リンゴなど) | 0.5〜1.5% | 年2回までが目安 |
濃度の計算例としては、水1リットルに対して尿素2gを加えると0.2%、10gで1%の濃度になります。
散布の時間帯と気象条件を選ぶ
葉面散布は早朝または夕方、気温が低く風の穏やかな時間帯に行うのが基本です。高温時や直射日光下での散布は、葉焼けや蒸発による効果減少につながります。加えて、雨の前後は避け、施用後しばらくは葉面が乾くまで水に当たらないようにするのが理想です。
散布機器と手順のポイント
尿素液はジョウロやスプレーボトルなどで散布可能ですが、広い範囲では噴霧器の使用がおすすめです。散布時は葉の表面だけでなく裏側にもまんべんなくかかるように意識しましょう。液が垂れ落ちるほどの量ではなく、霧状に薄く広がる程度が適量です。
葉面散布を均一に行うためには、高品質な噴霧器が必要です。「マルハチ産業の蓄圧式噴霧器」は、使いやすさと耐久性で定評があり、広範囲の散布作業にも適しています。
使い方のコツと保存方法

尿素は非常に便利な肥料ですが、使い方や保管の仕方によっては効果が半減したり、安全性に問題が生じたりすることもあります。ここでは、尿素を賢く活用するためのコツと保存の注意点をまとめます。
適量施用のコツを押さえる
尿素の窒素濃度は非常に高いため、「少なめから始める」ことが失敗しないポイントです。初めて使う場合や植物が弱っている時には、基準の8〜9割の量に抑えるのがおすすめです。また、複数回に分けて施用する「分施」も、過剰を避けながら長く効かせる方法として有効です。
他の肥料や資材との相性に注意
前述の通り、尿素はアルカリ性の資材(石灰、草木灰など)と同時に使うと、化学反応でガスが発生し、窒素分が揮発してしまいます。これを避けるには、尿素とアルカリ性肥料の施用間隔を最低でも3~5日(冬季は7日以上)あける必要があります。
保存方法は湿気対策が最優先
尿素は吸湿性が高く、空気中の水分を吸って結晶が溶けてしまう性質があります。このため、開封後は密閉容器に移し替え、乾燥した冷暗所に保管するのが基本です。湿気が多い場所では固まりやすく、施用時に計量しにくくなるため、袋のまま放置するのは避けましょう。
尿素肥料の保存には、湿気を防ぐ密閉容器が不可欠です。「アイリスオーヤマの密閉ストッカー」は、しっかりと密閉でき、肥料の品質を長期間維持します。
| 保存方法 | 推奨される状態 |
|---|---|
| 容器 | 密閉できるプラスチックまたは金属製 |
| 場所 | 直射日光の当たらない乾燥した室内 |
| 温度 | 常温(高温多湿は避ける) |
| 開封後 | 1シーズン以内に使い切るのが理想 |
保存状態が悪いと尿素が固まり、肥料としての均一な施用が困難になります。残量が少なくなった場合は、用途に応じて水肥にするなど早めに使い切る工夫も必要です。
尿素肥料の作り方と希釈の基本
尿素は水に溶けやすいため、水肥(液肥)や葉面散布として使用する場合、自分で希釈液を作る必要があります。ここでは、尿素肥料の作り方や希釈時の基本ルールについて解説します。
希釈の基本:濃度と分量の計算方法
尿素の希釈は、目的や作物に応じた「濃度」が重要なポイントです。目安となる濃度を把握しておけば、安全かつ効果的な施肥が可能です。
尿素肥料の希釈には、正確な計量が不可欠です。そこでおすすめなのが、デジタル表示で1g単位の計量が可能な「タニタ キッチンスケール」です。コンパクトで使いやすく、肥料の計量にも最適です。
| 希釈目的 | 尿素量 | 水の量 | 濃度目安 |
|---|---|---|---|
| 葉面散布(野菜・果樹) | 5g | 1L | 約0.5% |
| 葉面散布(米・麦) | 10g〜20g | 1L | 1〜2% |
| 水肥(液肥として根元に) | 20g | 6L | 約0.3% |
※上記は目安です。植物の種類や生育状況に応じて濃度は調整してください。
例えば、1%の液肥を作る場合、水1リットルに尿素10gを加えるだけで完成します。スプーン1杯=約5gなので、キッチン用計量スプーンでも代用できます。
作り方の手順
-
清潔な容器に、必要な量の水を用意する(常温が最適)。
-
尿素を規定量加える。
-
よくかき混ぜて完全に溶かす。
-
すぐに使わない場合は密閉容器で保管する。
作成した液肥は長期間放置せず、なるべく早めに使い切ることをおすすめします。夏場は特に劣化しやすいため、必要な分だけ作るのが理想的です。
他の肥料や農薬との混合時の注意
尿素は農薬と混ぜて使用することで、吸収効果を高めるという利点もありますが、農薬の種類によっては相性が悪い場合もあります。混合前には、必ず製品ラベルや使用説明を確認してください。濃度が高すぎると、農薬とあわせて葉焼けを起こすこともあるため注意が必要です。
尿素の肥料としての使い方がよくわかりません。

「尿素の使い方が難しそう」と感じる方も多いかもしれませんが、基本的なルールさえ押さえれば扱いやすい肥料です。この章では、初心者の方でも理解できるよう、使い方の流れと注意点をまとめてご紹介します。
基本の使い方:3つの施肥方法
尿素は主に「元肥」「追肥」「葉面散布」の3つの使い方があります。使う場面によって適切な方法を選びましょう。
| 施肥方法 | タイミング | 特徴 |
|---|---|---|
| 元肥 | 植え付け前・種まき前 | 土に混ぜて使用。根に直接触れないよう注意。 |
| 追肥 | 成長途中で必要に応じて | 成長を促す。作物によって間隔を調整。 |
| 葉面散布 | 栄養不足の改善や補助的に | 即効性が高く、葉の色が改善しやすい。 |
なお、尿素は単肥であるため、リン酸やカリなど他の栄養素は別途補う必要があります。複合肥料と一緒に使うとバランスの良い施肥が可能です。
よくある疑問:どれくらい使えばいいの?
使用量は作物や栽培面積によって変わりますが、目安は以下の通りです。
-
家庭菜園(1㎡あたり):10〜15g
-
果樹の根元(1㎡あたり):5〜10g
-
プランター栽培(5号鉢):約2g
少量から始めて、植物の反応を見ながら徐々に調整すると失敗しにくくなります。
間違いやすいポイントに注意
尿素は水に溶けやすいため、施用後すぐに雨が降ると流れてしまいます。雨の直前や灌水直後の施用は避けましょう。また、土の表面に置くだけでは揮発してしまう可能性もあるため、軽く混ぜ込むか深層施肥が理想です。
加えて、アルカリ性肥料(石灰・草木灰など)と一緒に使うと化学反応が起こり、尿素の効果が失われることがあります。これらは施肥の間隔を空けて使用しましょう。


尿素とは肥料としてどんな特徴と使い方があるのか総まとめ
-
約46%の窒素を含む高濃度な窒素肥料である
-
水に溶けやすく中性で、さまざまな土壌に適応しやすい
-
葉や茎の成長を促進し、クロロフィルの生成を助ける
-
即効性があり、特に追肥や葉面散布に向いている
-
成長初期や黄変した葉への施用で速やかな改善が期待できる
-
土壌中で加水分解されてからアンモニア態窒素に変化する
-
使いすぎると肥料焼けや水質汚染の原因になりうる
-
葉面散布には作物ごとに適切な濃度を守る必要がある
-
夏場は2~3日で効き始め、冬は1週間以上かかることもある
-
根に直接触れないように元肥としては深層施肥が推奨される
-
アルカリ性肥料とは間隔を空けて施用すべきである
-
尿素と硫安は使い方や土壌の性質によって選択する
-
尿素は葉面散布や液肥として自作でき、希釈が簡単である
-
密閉して乾燥した場所で保管し、吸湿や固結を防ぐ必要がある
-
他の肥料と併用する際は成分の相性とタイミングに注意が必要