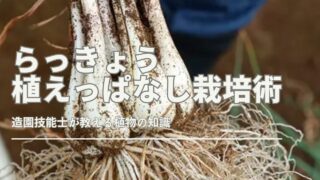ポーチュラカ植えっぱなしで長く咲かせるコツと枯れる原因と対策

ポーチュラカは、暑さや乾燥に強く、初心者でも育てやすい人気の植物です。そんな魅力的なポーチュラカを「植えっぱなし」で楽しみたいと考える方も多いのではないでしょうか。しかし、実際のところ屋外で冬越しできますか?という疑問や、ポーチュラカは毎年咲きますか?といった声もよく聞かれます。
この植物は生育が旺盛で、放っておくと伸びすぎたらどうすればいいですか?と悩むケースもあります。また、ポーチュラカは何月まで咲く?といった開花期間の目安も気になるポイントです。
この記事では、「ポーチュラカ植えっぱなし」を検討している方に向けて、冬越しの方法や年間管理のコツ、花を長く楽しむための工夫まで、わかりやすく解説していきます。植えっぱなしでも失敗しないために、ぜひ最後までチェックしてみてください。
-
屋外でポーチュラカを冬越しさせる際の注意点と対策
-
毎年咲かせるための管理方法や更新手段
-
茎が伸びすぎたときの切り戻し方法と効果
-
開花時期の目安と長く花を咲かせるための工夫

ポーチュラカ植えっぱなしは可能か?

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | スベリヒユ |
| 学名 | Portulaca oleracea |
| 特徴 | 地面を這うように広がる一年草で、茎や葉に光沢があり、黄色い花を咲かせます。 |
| 分布 | 世界中の温暖な地域に広く分布し、日本では全国的に見られます。 |
| 食用 | 若葉や茎をおひたしや和え物などに利用し、酸味とぬめりが特徴です。 |
| 栽培 | 乾燥や暑さに強く、日当たりの良い場所で容易に育ちます。 |
| 注意点 | 繁殖力が強く、他の植物を圧迫することがあるため、管理が必要です。 |


屋外で冬越しできますか?
ポーチュラカの冬越しについては、「屋外での管理は基本的に難しい」と考えておくのが無難です。ポーチュラカは暑さと乾燥に強い一方で、寒さに非常に弱いためです。
この植物は南米原産で、耐寒性が低く、気温が5℃を下回ると枯れるリスクが高まります。霜が降りる地域では特に注意が必要です。多くの場合、霜が直接葉に当たることで一夜にして枯れてしまうこともあります。
冬越しに適した気温と環境
ポーチュラカを屋外で冬越しさせるには、冬でも気温が5℃以上を保てる地域であることが条件となります。ただし、風や湿気などもダメージの原因になるため、気温だけでなく環境全体を考慮する必要があります。
ポーチュラカを冬越しさせる際、霜や寒風から守るために「植物用防寒カバー」が役立ちます。通気性がありながら保温性も高く、植えっぱなしでも安心です。私もこのカバーを使って、ポーチュラカを無事に冬越しさせることができました。設置も簡単で、繰り返し使用できるのが嬉しいポイントです。詳しくはこちらをご覧ください。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 最低耐寒温度 | 約5℃ |
| 霜への耐性 | ほぼなし(直撃すると枯れる) |
| 適した越冬環境 | 屋内または簡易温室がおすすめ |
プランターや鉢植えでの対策
地植えでは対策が難しいため、鉢やプランターで育てている場合は、寒くなる前に室内に取り込むのが一般的です。南向きの窓辺や温度の安定した玄関などが管理しやすいでしょう。
ただし、室内に入れると光量が不足しがちになるため、日当たりを確保する工夫も必要です。また、水やりの頻度も控えめにし、株元にのみ与えるようにしましょう。
ビニールカバーなどの簡易対策
一時的な寒さ対策として、ビニールシートや不織布を使って保温する方法もあります。特に夜間の冷え込みが強い地域では有効ですが、根本的な解決にはなりにくく、日中との温度差で蒸れてしまうリスクもあります。
このように、屋外での冬越しは工夫次第で可能な場合もありますが、失敗のリスクが高いため、基本的には屋内に取り込む方が安心です。
ポーチュラカは毎年咲きますか?

ポーチュラカは多年草に分類されますが、日本の気候では一年草として扱われることが多い植物です。そのため、毎年咲かせるには適切な環境づくりと管理が必要になります。
本来は多年草であるため、冬の寒さを避けることができれば翌年も咲かせることが可能です。ただし、寒冷地や霜が多い地域では屋外での越冬が難しく、枯れてしまうことが一般的です。
室内管理で毎年楽しむ方法
鉢植えにして室内で越冬させた場合、翌年も同じ株から花を咲かせることができます。このときのポイントは、冬の間に株を休眠状態にし、過湿にならないよう注意して管理することです。
春になると暖かさに反応して新芽が出てきますので、それに合わせて日照と水やりを調整していきます。
種や挿し芽での更新も有効
ポーチュラカはこぼれ種や挿し芽でも増やせる植物です。そのため、毎年苗を買わずとも、秋に挿し芽をつくって室内で育てれば、翌年も開花が期待できます。
以下に、ポーチュラカの更新方法をまとめた表を示します。
| 方法 | 特徴・メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 挿し芽 | 確実に同じ品種が育つ | 秋に作る場合は室内管理が必須 |
| こぼれ種 | 自然発芽することもある | 品種が変わる、花が咲かない可能性も |
| 株の越冬 | 同じ株で翌年も楽しめる | 屋外では難しく、室内管理が基本 |
地植えでは一年草と割り切るのも一案
地植えの場合は越冬がほぼ不可能なため、毎年苗を購入して楽しむ方法もおすすめです。最近では品種も豊富になっており、花色や形を選ぶ楽しみもあります。
このように、ポーチュラカを毎年咲かせるには環境と管理方法が重要です。屋外のままでは難しいですが、挿し芽や室内での管理を取り入れることで、翌年も花を咲かせることができます。
伸びすぎたらどうすればいいですか?
ポーチュラカは生育が旺盛な植物で、気づくと茎が地面を這うようにどんどん伸びていきます。特に植えっぱなしにしておくと、花が先端にしか咲かず、中心部分がスカスカになりやすくなります。
このような状態になったときは「切り戻し(剪定)」を行うことで、株の形を整え、再び花付きの良い状態に戻すことができます。
ポーチュラカが伸びすぎた場合、剪定には「ガーデニング用ハサミ」が便利です。切れ味が良く、手にフィットするデザインで、長時間の作業でも疲れにくいです。私もこのハサミを使って、ポーチュラカの形を整えています。詳細はこちらからご確認いただけます。
切り戻しのタイミングと目安
ポーチュラカの茎が15〜20cm以上に伸び、株元の葉が少なくなってきたと感じたら切り戻しの合図です。花が減ってきた時期や、全体の形が乱れ始めたときもタイミングとして適しています。
| 目安の茎の長さ | 切り戻し推奨度 | 花付きへの影響 |
|---|---|---|
| 10cm未満 | 不要 | そのままでもOK |
| 15~20cm以上 | 実施した方が良い | 花が先端に偏りやすい |
| 30cm超 | 強く推奨 | 株全体のバランスが崩れる |
切り戻しの方法とポイント
切り戻しは、伸びすぎた茎を1/3〜1/2程度の長さにカットするだけで構いません。剪定ばさみを使い、葉のつけ根や節の上で切るようにすると、そこから新しい芽が出やすくなります。
また、切った茎は挿し芽にして増やすことも可能ですので、無駄なく活用できます。
切り戻し後の管理に注意
切り戻したあとは一時的に花が減りますが、2週間ほどで新芽とともに花が再び咲き始めます。この間は肥料を与えすぎず、日当たりと風通しを確保して、回復を待ちましょう。
強く切りすぎると株が弱ることもあるため、初めての剪定では慎重に進めると安心です。
ポーチュラカは何月まで咲く?

ポーチュラカは開花期間が長く、5月から10月ごろまで花を楽しめる夏の代表的な草花です。ただし、地域の気候や管理方法によって、咲く時期に多少の違いがあります。
一般的に、気温が20℃以上の日が続く期間に最もよく咲き、気温が下がってくる秋口には徐々に花数が減っていきます。
地域別の開花時期の目安
地域によって気温の下がる時期が異なるため、開花が終わる時期も変わります。以下の表は、主な地域ごとの「何月まで咲くか」の目安です。
ポーチュラカの開花を長く楽しむためには、適切な肥料が欠かせません。「花用液体肥料」は、栄養バランスが良く、花付きが向上します。私もこの肥料を使用して、ポーチュラカの美しい花を長期間楽しんでいます。使い方も簡単で、初心者の方にもおすすめです。詳しくはこちらをご覧ください。

| 地域 | 開花終了の目安時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 北海道 | 9月下旬頃まで | 秋の冷え込みが早いため短め |
| 関東・関西 | 10月中旬頃まで | 比較的長く楽しめる |
| 九州 | 10月下旬~11月初旬 | 暖かい地域ではより長く咲くことも |
花が咲き続ける条件とは?
ポーチュラカの花は「日照時間」に大きく左右されます。朝から日がよく当たる環境で管理していれば、秋でも長く咲かせることが可能です。また、枯れた花をこまめに摘み取る「花がら摘み」も、開花を促進する重要な作業です。
もう一つのポイントは、気温の変化に敏感な点です。特に朝晩の寒暖差が大きくなってくると、花が咲きにくくなり、開花は終了に向かっていきます。
寒さで咲かなくなる前に
気温が下がっても株自体がすぐに枯れるわけではありませんが、10℃を下回る頃から花は咲かなくなっていきます。そのため、できるだけ長く花を楽しみたい場合は、夜間の冷え込みから株を守る対策を取るとよいでしょう。
例えば、簡易的なビニール温室や、鉢を室内に取り込むことで、開花時期を延ばすことができます。これにより、最長で11月初旬まで花を楽しめるケースもあります。
ポーチュラカ植えっぱなしの注意点



冬越しは屋外かプランターか?
冬の管理方法を選ぶ際、ポーチュラカは「屋外でそのまま越冬させる」か「プランターで屋内に取り込む」かが大きな分かれ道になります。どちらが適しているかは、住んでいる地域の気温や管理のしやすさによって判断しましょう。
屋外での冬越しは原則おすすめしない
ポーチュラカは寒さに弱い植物で、気温が5℃を下回ると傷みやすくなります。特に霜や冷たい風が直接当たるような環境では、葉が黒く変色し、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。
| 条件 | 屋外冬越しの可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 気温が5℃以上をキープ | 条件付きで可能 | 短期間ならビニールで補強も |
| 霜が降りる地域 | 不可 | 枯れるリスクが非常に高い |
| 無霜地または暖地 | 難易度は下がる | 簡易保温があれば可 |
一方で、冬でも比較的暖かい地域や、霜の影響を受けにくい場所であれば、簡易的なカバーを施すことで屋外での冬越しができることもあります。ただし、あくまで例外的なケースとして考えておきましょう。
プランターは冬越しに最適な選択肢
プランターで育てている場合は、寒くなる前に室内へ移動させるのが安全です。特に11月以降は最低気温に注意し、寒波が予想される日は早めの対策が必要です。
プランターでの冬越しには以下のようなメリットがあります。
-
移動が簡単で管理しやすい
-
室内で温度調整が可能
-
冬の間も植物の状態を観察できる
ただし、室内に入れると光量が足りなくなりがちです。日当たりのよい窓辺などを選び、できるだけ昼間は明るい場所で管理しましょう。
冬越しのために植え替えるのも有効
地植えで育てている場合でも、寒さが厳しくなる前に掘り上げて鉢に植え替えることで冬越しがしやすくなります。根を傷つけないよう注意し、軽く剪定してから屋内に取り込むのがコツです。
ビニールを使った冬越し対策

屋外でポーチュラカを冬越しさせたい場合、ビニールを活用した簡易的な保温対策が有効です。特に寒冷地ではなく、比較的温暖な地域であれば、ビニールを使うことで霜や風から守る効果が期待できます。
ビニールを使うメリットと注意点
ビニールの最大の利点は、外気を直接植物に当てないことです。透明な素材を使えば、光を取り込みながら温度を保つことができます。また、コストも比較的安価で手に入るため、気軽に取り入れられるのも魅力です。
ただし、密閉しすぎると内部が蒸れたり、カビの原因になるため、通気性も考慮しなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用素材 | 透明ビニール、厚手の園芸用シートなど |
| 通気性 | 両端を開ける、日中は一部開けるなどで調整 |
| 設置方法 | 支柱を使って簡易温室のように覆う |
プランターへの使い方の工夫
プランターの場合は、支柱を立ててビニールをテントのように被せる形が一般的です。隙間から風が入らないよう、下部を重しで押さえるか、紐で固定すると安定します。
日中はビニール内の温度が上がりすぎることもあるため、風通しを意識して、一部を開けるなどの工夫が必要です。夜間はしっかり覆って保温を心がけましょう。
地植えでのビニール活用例
前述の通り、地植えでの冬越しは基本的に難しいですが、どうしても試したい場合にはビニールトンネルや不織布カバーの併用が考えられます。それでも厳冬期には限界があり、根の凍結までは防げない可能性があるため、完全な対策にはなりません。
このように、ビニールは手軽な冬越しアイテムとして有効ですが、使い方や管理に細やかな注意が必要です。屋外での冬越しを目指すなら、ビニール対策と室内管理の両方を検討すると安心です。
ポーチュラカの地植えは向いている?
ポーチュラカは暑さと乾燥に非常に強く、地植えでもよく育つ丈夫な植物です。ただし、冬越しやスペースの確保など、いくつかの条件を押さえておく必要があります。
地植えのメリットと注意点
地植えにすると、ポーチュラカは根をしっかりと張って広がり、ふんわりとしたボリュームのある花壇を作ることができます。水やりの頻度も減るため、管理の手間が少ない点も魅力です。
ポーチュラカの栽培をより快適にするために、「自動散水タイマー」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。設定した時間に自動で水やりができ、旅行中でも安心です。私もこのタイマーを使って、ポーチュラカの水やり管理がとても楽になりました。詳細はこちらからご確認いただけます。
| 項目 | 地植えの特徴 |
|---|---|
| 成長スピード | 早く、広がりやすい |
| 管理の手間 | 水やり・肥料少なめでOK |
| 冬越しの難易度 | ほぼ不可能(特に霜が降りる地域) |
| 他の植物との相性 | 匍匐性のため、スペースを取る点に注意 |
日当たりと風通しがカギになる
地植えする場所としては、「日当たりと風通しの良い場所」を選ぶことが重要です。ポーチュラカは日光に反応して開花するため、日陰では花つきが悪くなります。
また、周囲に木や壁があると風通しが悪くなり、過湿になりやすくなるため注意が必要です。特に梅雨時期などは、過湿による根腐れや病害虫のリスクもあります。
肥料は控えめでOK
前述の通り、地植えでは肥料がほとんど必要ありません。土壌が極端に痩せている場合を除き、元肥を混ぜる程度で十分です。与えすぎると逆に茎が徒長し、株の形が乱れやすくなるので、注意しましょう。
こぼれ種で自然に増えますか?

ポーチュラカは園芸品種のため、種ができにくいタイプが多く、こぼれ種による自然繁殖はあまり期待できません。とはいえ、すべての品種が種を作らないわけではないため、ケースによってはこぼれ種から芽が出ることもあります。
こぼれ種の発芽には条件がある
こぼれ種で増えるかどうかは、気候や土の状態、品種によって異なります。温暖な地域で冬を越したり、雨風が当たりにくい場所に種が落ちた場合などには、自然発芽することもあります。
ただし、発芽しても親株と同じ性質の花が咲くとは限らない点に注意が必要です。特にF1品種(交配種)の場合は、性質がばらついたり、そもそも花をつけないこともあります。
| 条件 | 発芽の可能性 | 備考 |
|---|---|---|
| 温暖な地域 | あり(確率は低め) | 条件が良ければ自然発芽することもある |
| 交配種(F1品種) | ほぼなし | 種ができないか、性質が変わることが多い |
| 挿し芽との比較 | 挿し芽の方が確実 | 種よりも確実に増やせる方法 |
確実に増やしたいなら「挿し芽」
こぼれ種に頼るよりも、「挿し芽」で増やす方が確実で効率的です。ポーチュラカは茎を切って土に挿しておくだけで簡単に根を出します。適期は5月〜9月で、特に夏場は発根が早いため、初心者でも扱いやすい方法です。
また、挿し芽であれば元の株と同じ花が咲くため、花の色や性質を維持したい場合にも適しています。
花後の管理で種を狙うなら
こぼれ種を試したい場合は、花がら摘みをあえて控えてみると、運が良ければ種がつくことがあります。その際は、鞘が割れてこぼれる前に回収し、紙袋などで保存しておきましょう。
ただし、こぼれ種から育てた苗は生育が安定しないこともあるため、楽しみとしてチャレンジする程度にとどめておくのがよいかもしれません。
いつまで咲くかの目安を解説
ポーチュラカは5月頃から咲き始め、気温が高い時期に元気に花を咲かせる植物です。開花時期は地域や環境によって若干前後しますが、基本的には「10月頃まで咲く」と考えておくとよいでしょう。
特に花数が多くなるのは7〜9月の間で、日差しが強いほど花つきが良くなります。反対に、日照時間が短くなったり、気温が15℃を下回り始めると、次第に開花数が減っていきます。
地域別・開花終了時期の目安
地域によって開花が続く時期には差があります。以下の表は、ポーチュラカの「咲き終わり時期」の目安です。
| 地域 | 咲き終わりの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 9月中旬~下旬 | 朝晩の冷え込みが早く、終了も早め |
| 関東・関西 | 10月中旬 | 気温が下がると徐々に花が減る |
| 九州・沖縄 | 10月下旬~11月初旬 | 温暖な地域では長く咲き続けることも可能 |
光と気温の関係が重要
ポーチュラカの花は、太陽の光に反応して開花する「日照反応性植物」です。そのため、曇りや雨が続くと一時的に花が咲かなくなることもあります。
また、最低気温が10℃を下回るようになると、花が開かなくなるだけでなく、株自体も成長を止めるようになります。寒さが本格的になる前に、次の育成の準備を始めるタイミングです。
長く咲かせるための工夫
環境が合えば11月初旬まで花を楽しめることもあります。少しでも長く開花を楽しむためには、以下の点に注意するとよいでしょう。
-
枯れた花はこまめに摘み取る(花がら摘み)
-
液体肥料を月1回ほど与える
-
日照時間を確保できる場所に鉢を移動する
秋口でも工夫次第で、ポーチュラカの開花期間を延ばすことができます。
枯れる原因は何ですか?

ポーチュラカは丈夫で育てやすい植物として知られていますが、環境が合わない場合やお手入れを誤ると、思わぬ形で枯れてしまうことがあります。
枯れる原因は一つではなく、複数の要因が重なって起きるケースも多いため、観察と早めの対処が重要です。
主な枯れる原因と対処法
以下は、ポーチュラカが枯れる原因としてよく見られるものです。
| 原因 | 症状 | 対処法 |
|---|---|---|
| 過湿・根腐れ | 下葉が黄色くなり、茎がブヨブヨになる | 水やりを控え、風通しの良い環境にする |
| 寒さによるダメージ | 葉が黒ずみ、全体がしおれる | 室内に取り込み、5℃以上で管理する |
| 霜に当たる | 一夜で株全体が茶色に枯れる | 霜の前に鉢を移動する、保温対策をする |
| 肥料の与えすぎ | 茎ばかり伸びて花が減り、全体が弱る | 肥料は控えめにし、与える頻度を見直す |
| 病害虫(アブラムシなど) | 葉の裏や茎に虫が付き、葉が萎れる | 殺虫剤を使用し、剪定で風通しを改善する |
過湿には特に注意が必要
ポーチュラカは乾燥に強い反面、過湿状態が続くと根腐れを起こしやすくなります。特に梅雨時期や夏の夕立後などは、鉢の水はけを確認することが大切です。
また、受け皿に水がたまったままになっていると、根が常に湿った状態になり、病気が進行しやすくなります。
寒さ対策を忘れずに
寒さもポーチュラカが枯れる主な原因の一つです。地植えでは防寒が難しいため、鉢植えに切り替えるのも一つの方法です。室内で管理すれば、春まで元気に過ごさせることが可能です。
このように、日常の管理を少し工夫するだけで、ポーチュラカを健康に保つことができます。状態の変化に早く気づけるよう、日々の観察を忘れずに行いましょう。
ポーチュラカに肥料をあげる時期はいつですか?
ポーチュラカは栄養分の少ない土でも比較的元気に育つ植物ですが、適切な時期に肥料を与えることで、花つきが良くなり、長く美しい姿を楽しめます。特に鉢植えの場合は肥料不足に陥りやすいため、時期と頻度の把握が大切です。
肥料を与える適切な時期
肥料を与えるタイミングは、「植え付け時」と「開花期に入る頃」の2つが基本です。具体的には以下の時期が目安になります。
| タイミング | 肥料の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 植え付け時(5~7月) | 緩効性化成肥料 | 土に混ぜ込むことで長期間ゆっくり効く |
| 開花期(6~9月) | 液体肥料(月1回) | 花つきを良くするため、追肥として与える |
植え付け時に緩効性の肥料を混ぜておけば、最初の1~2ヶ月は追肥が不要なケースもあります。土の状態を見ながら調整しましょう。
鉢植えと地植えでの違いに注意
ポーチュラカを鉢で育てている場合は、土の栄養分が流れやすいため、地植えよりも肥料の管理が重要です。定期的に薄めた液体肥料を与えることで、花を次々に咲かせる力が持続します。
一方で、地植えの場合は基本的に肥料を与えなくても問題ありません。逆に肥料を多く与えすぎると、花が減って葉や茎ばかりが育ってしまう「徒長(とちょう)」の原因になります。
肥料を与えない方がよい場合もある
株がすでに大きく育っている場合や、葉が濃い緑で勢いのある状態なら、無理に肥料を追加する必要はありません。また、涼しくなり始める9月以降は肥料を控えることで、冬に向けて株の健康を保つことができます。
植えっぱなしに適した管理方法

ポーチュラカを「植えっぱなし」で育てたい方にとって、日々の管理の手間を減らしつつ元気に育てるための工夫がポイントになります。特に庭や広い花壇では、毎日の水やりや手入れが難しいため、自然に近い管理方法を知っておくと便利です。
基本は「日当たり」と「水はけ」
ポーチュラカの植えっぱなし管理で最も重要なのは、日当たりと水はけの良い環境に植えることです。日光が不足すると花が咲かず、過湿な場所では根腐れが起きやすくなります。
| 環境条件 | 適した状態 |
|---|---|
| 日当たり | 1日中よく日の当たる場所 |
| 水はけ | 砂やパーライトを混ぜた土壌 |
| 風通し | 密集しないよう株間を空ける |
このような環境を最初に整えておけば、その後の管理はぐっと楽になります。
水やりの頻度を減らすには
植えっぱなしで水やりの手間を減らすためには、地植えが向いています。ポーチュラカは乾燥に強いため、自然降雨だけで十分に育つことが多いです。鉢植えの場合は、表面の土がしっかり乾いてから水を与えるようにすると過湿を防げます。
また、マルチング材(バークチップや腐葉土)を土の表面に敷いておくことで、乾燥を防ぎつつ雑草対策にもなります。
最低限の手入れで花数を維持する
植えっぱなしでも長く花を楽しむためには、最低限のメンテナンスが必要です。特に、次の2つは習慣にしておくと効果的です。
-
枯れた花の除去(花がら摘み):新しい花が咲きやすくなります。
-
茎の切り戻し:株全体の形を整え、分枝を促す効果があります。
こうした作業は月1~2回程度でも効果があるため、時間がない方でも取り入れやすいポイントです。
このように、最初の環境づくりをしっかり行い、必要最小限のケアを続けることで、ポーチュラカを「植えっぱなし」でも長く元気に楽しむことができます。


アウディ高級車のように手軽に楽しめるポーチュラカ植えっぱなしのまとめ
-
ポーチュラカは地植えで広がりやすく管理が楽
-
日当たりと水はけの良い場所が最適
-
植えっぱなしでも開花期間が長く楽しめる
-
鉢植えよりも地植えの方が乾燥に強い
-
寒さに弱いため屋外越冬は地域によって制限される
-
プランターなら冬は室内に取り込める
-
ビニールでの簡易保温も対策として有効
-
茎が伸びすぎたら切り戻しで再び花を咲かせやすい
-
肥料は控えめでよく、徒長を防げる
-
夏に強く、水やり頻度が少なくて済む
-
花がら摘みで長く咲き続けさせることができる
-
こぼれ種からの発芽は不安定で挿し芽の方が確実
-
植えっぱなしでも月1〜2回の簡単な手入れで十分
-
日照が花つきに大きく影響するため日陰は避ける
-
開花は地域により11月初旬まで楽しめる場合もある