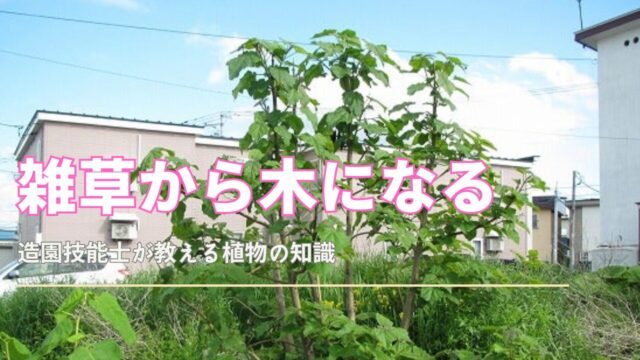防虫ネット ダイソーで害虫対策!設置方法と選び方ガイド

植物を虫から守るために欠かせないアイテムのひとつが「防虫ネット」です。中でも100円ショップのダイソーで手軽に購入できる防虫ネットは、コストを抑えつつしっかりとガーデニングを楽しみたい人に人気があります。この記事では、防虫ネット ダイソーをキーワードに、初めて使う方にもわかりやすく基礎知識や活用方法をまとめました。
具体的には、「メリット・デメリットは?」といった使用前に知っておきたいポイントから、「何年くらい使えますか?」という耐久性、「防虫ネットは水やりのたびに外すの?」という使用時の疑問までを丁寧に解説しています。また、「色は何色が良いですか?」という色選びのコツや、「ダイソーの防虫ネットが売り切れ?サイズの選び方も解説」といった購入時の注意点にも触れています。
防虫ネットを初めて使う方も、より快適に使いたい方も、このページを通してしっかり準備を整えましょう。
-
ダイソーの防虫ネットの種類や選び方がわかる
-
防虫ネットのメリットとデメリットを理解できる
-
防虫ネットの耐用年数や正しい使い方を知ることができる
-
サイズや色の違い、使用シーンに応じた活用法がわかる

防虫ネット ダイソーはコスパ最強?



メリット・デメリットは?
防虫ネットを使うことで得られる利点は多くありますが、一方で注意点も存在します。ここでは、使用前に知っておきたいメリットとデメリットを整理してご紹介します。
防虫ネットを効果的に設置するには、適切な支柱が欠かせません。「siawadeky 支柱 ジョイント 30個セット」は、直径16mmの支柱を簡単に連結できるジョイントパーツです。耐久性のあるプラスチック製で、再利用も可能。家庭菜園やプランター栽培に最適なアイテムです。
メリット:害虫から植物を守れる
最大の利点は、やはり害虫の侵入を物理的に防げる点です。特に無農薬で家庭菜園を行いたい場合、防虫ネットは非常に有効です。アブラムシやコナガ、ハモグリバエといった虫の被害から苗や野菜を守ることで、健康に育てやすくなります。
また、ネットが日よけの役割を果たす場合もあり、直射日光による葉焼けを防止する副次効果も期待できます。
メリット:農薬の使用量を減らせる
防虫ネットを使用することで、農薬の使用を最小限に抑えることができます。これは、特に家庭で食用の野菜を育てる際に重視されるポイントです。小さなお子さんがいる家庭では、安全面からも大きな安心につながります。
デメリット:設置・管理に手間がかかる
一方で、ネットの設置にはある程度の手間がかかります。支柱やクリップを用意し、しっかりと覆わなければ効果を十分に発揮できません。また、風の強い日にはネットがあおられて外れることもあるため、固定方法にも注意が必要です。
デメリット:水やりや収穫がしにくい
防虫ネットをかけると、ネットを外さなければ水やりや収穫が難しくなる場合があります。特に大きめの鉢や地植えで育てる場合は、毎回ネットを持ち上げる作業が発生し、煩雑に感じるかもしれません。
メリット・デメリットまとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 害虫防止、農薬削減、日よけ効果 |
| デメリット | 設置の手間、水やり・収穫のしづらさ |
何年くらい使えますか?

防虫ネットは一度購入すれば長く使えるアイテムですが、使用環境や取り扱い方法によって寿命は大きく変わります。ここでは、一般的な耐用年数と長持ちさせるコツをご紹介します。
通常の使用での耐用年数は2〜3年
市販されている一般的な防虫ネットは、日常的な使用で2年から3年程度の耐用年数があると言われています。これは主に屋外使用を前提とした場合で、直射日光や風雨にさらされる状況では、素材の劣化が進みやすいためです。
ネットが破れたり、目が粗くなると防虫効果が低下するため、目に見える劣化があれば早めの交換が望まれます。
使用後の保管が寿命に大きく影響
ネットの寿命を延ばすには、使わない期間の保管方法も重要です。濡れたまま放置するとカビの原因になったり、紫外線の強い場所に保管すると素材が脆くなります。使用後は汚れを落とし、風通しの良い日陰で乾かしてから保管することがポイントです。
素材によって耐久性に差がある
防虫ネットの素材は、主にポリエステルやナイロンが使われています。ナイロン製は柔らかく扱いやすい反面、紫外線にやや弱い傾向があります。ポリエステル製は比較的耐久性が高く、風雨にも強いのが特徴です。
以下に、素材別の特徴を表にまとめました。
| 素材 | 特徴 | 耐用年数(目安) |
|---|---|---|
| ナイロン | 柔らかく加工しやすいが劣化しやすい | 約2年 |
| ポリエステル | 耐久性があり屋外に強い | 約3年 |
防虫ネットは水やりのたびに外すの?
防虫ネットを設置した状態での水やりは、少し気になるポイントかもしれません。ここでは、水やり時にネットを外す必要があるのかどうか、また効率的な方法について詳しく解説します。
基本的には外さずに水やりできる
ほとんどの防虫ネットは、ある程度の水通し性を持っているため、そのままの状態で水やりをしても問題ありません。細かな網目でも、水は自然に通過して土に浸透します。ただし、水量が少なすぎると十分に行き渡らないこともあるため、少し多めに注ぐよう意識すると安心です。
条件によっては一部外した方が良い
植物の種類や栽培方法によっては、ネット越しの水やりが適さないケースもあります。特に、葉が密集していて水が十分に届きにくい植物や、鉢が深く根が張っているものは、水やりのたびにネットを一部めくる必要があるかもしれません。
また、霧吹きやシャワータイプのジョウロを使うと、葉全体に水が行き渡りやすくなります。
長期間使うなら作業性も考慮
毎回ネットを外すのが面倒な場合は、ファスナー付きや開閉できるタイプの防虫ネットを選ぶと便利です。水やり以外にも、収穫や追肥の際に作業がしやすくなるため、長期的な使用を考えている方には特におすすめです。
色は何色が良いですか?

防虫ネットの色は白が一般的ですが、最近では黒やグレーなど複数のバリエーションがあります。色によって期待できる効果が異なるため、用途に応じて選ぶことが大切です。
白色ネットは日光を通しやすい
もっとも多く流通しているのが白色タイプの防虫ネットです。白は日光を比較的よく通すため、光合成を妨げずに植物を育てることができます。さらに、虫が視認しにくいとも言われており、野菜や花など幅広い植物に使われています。
黒色ネットは遮光効果が高い
黒いネットは遮光性が高く、強い日差しを抑える効果があります。夏場に直射日光で葉焼けしやすい植物には有効ですが、その分光合成に必要な光が不足する恐れもあるため、日照時間の短い地域や季節には注意が必要です。
また、黒は熱を吸収しやすく、気温が上昇しやすくなる可能性もあります。
グレーやシルバーはバランス型
中間色であるグレーやシルバーのネットは、白と黒の中間的な性質を持ちます。適度な遮光効果と通気性を備えているため、日差しの強い地域や、多くの植物を一括でカバーしたい場合に適しています。
色ごとの特徴まとめ表
| 色 | 特徴 | 適した用途 |
|---|---|---|
| 白 | 光をよく通し、虫が視認しにくい | 野菜、花、家庭菜園全般 |
| 黒 | 遮光性が高く、夏場の葉焼け防止に効果的 | 強い日差しが当たる場所 |
| グレー系 | 光と影のバランスが良く、多目的に使いやすい | 複数の植物を一括でカバーしたい |
ダイソーの防虫ネットが売り切れ?サイズの選び方も解説
ダイソーの防虫ネットは手軽な価格と実用性から人気が高く、店舗によっては品切れ状態が続くこともあります。ここでは売り切れ時の対応方法と、適切なサイズの選び方について解説します。
売り切れが多い理由と代替手段
ダイソーの防虫ネットは季節商品として扱われることが多く、特に春から夏にかけて需要が集中します。このため、在庫があってもすぐに売り切れてしまうことがあるのです。
売り場で見つからない場合は、同じく100均のセリアやキャンドゥで探してみるのも一つの方法です。また、ガーデニング用品コーナーではなく、日用品やアウトドア関連の売り場に陳列されていることもあるため、店舗スタッフに問い合わせてみると良いでしょう。
防虫ネットのサイズ選びの基本
防虫ネットにはさまざまなサイズがありますが、植物の背丈や育成スペースに合ったサイズを選ぶことが大切です。小さすぎると風でめくれたり、逆に大きすぎると扱いにくくなるため、以下のような目安で選ぶと失敗しにくくなります。
| 使用目的 | 推奨サイズ例 | 特徴 |
|---|---|---|
| プランター栽培 | 幅1m×長さ2m程度 | 手軽に設置できて汎用性高い |
| 地植えの菜園 | 幅2m×長さ5m以上 | 支柱と併用でしっかり覆える |
| 室外機や網戸用 | 幅80cm〜100cm前後 | 小型サイズで十分対応可能 |
サイズが合わないときの工夫
もし適切なサイズが見つからない場合は、2枚を結束バンドなどでつなげて使う方法があります。また、少し大きめのものを折り返して使うのも有効です。サイズにこだわり過ぎず、柔軟に対応することが重要です。
防虫ネット ダイソーの種類と使い方



網戸の使い方
防虫ネットを導入する目的の一つに、家の中への虫の侵入を防ぐことがあります。ここでは、網戸と防虫ネットを併用する場合の使い方や注意点について説明します。
網戸と防虫ネットの違い
網戸と防虫ネットは似ているようで用途が異なります。網戸は窓やドアに常設して虫の侵入を防ぐものですが、防虫ネットは植物や室外機、または一時的な屋外活動の際に使用することが多いです。両者を適切に使い分けることで、快適な生活環境を維持できます。
網戸に直接貼って使う方法
防虫ネットは、網戸の破れや劣化を補う目的でも使うことが可能です。破れた部分に防虫ネットを重ねてテープやマジックテープで貼り付けるだけで、一時的な修理になります。専用の網戸補修用シールもありますが、防虫ネットでも十分代用できます。
換気と防虫を両立させる工夫
換気を重視したい場合は、網戸のメッシュが細かすぎないものを選ぶことがポイントです。防虫ネットを外側に重ねることで、虫の侵入をより確実に防げますが、通気性が下がる場合があるため、風通しの良い場所を確保するか、日中のみ開放するなどの工夫が必要です。
網戸の破れや劣化が気になる方には、「S.fields.inc ステンレスネット ソフト 防鼠金網」がおすすめです。柔軟性のあるステンレス製で、網戸の補修や防虫対策に最適。耐久性が高く、長期間使用できます。
室外機の活用法

防虫ネットは植物や室内空間だけでなく、室外機まわりの対策としても有効です。特にエアコンの室外機は虫や落ち葉が侵入しやすいため、ネットで覆うことでメンテナンスの負担を軽減できます。
室外機に防虫ネットを使う目的
室外機は吸気と排気を繰り返す構造上、小さな虫やゴミが内部に入りやすい場所です。その結果、冷却効率の低下や異音の原因になることもあります。これを防ぐため、防虫ネットで覆うことで、異物の侵入リスクを下げることができます。
設置方法のポイント
防虫ネットを使う際には、空気の流れを妨げないように余裕を持って設置することが重要です。ネットが吸気口や排気口に密着してしまうと、逆に室外機の動作に支障をきたすおそれがあります。以下のような方法で取り付けると安心です。
-
支柱や金網フレームで距離を取る
-
マジックテープや結束バンドで軽く固定する
-
通気性のある素材を選ぶ
防虫ネットで室外機カバーは代用可能か?
専用の室外機カバーと比べると、防虫ネットは価格面で手軽に試せる反面、耐久性やデザイン性にはやや劣ります。目的が虫やゴミの侵入防止であれば十分代用できますが、雨よけや美観も重視したい場合は、専用カバーと併用するのもおすすめです。
ダイソーで防虫ネットの支柱の選び方
防虫ネットを効果的に使うには、ネットそのものだけでなく「支柱」の選び方も重要です。特に家庭菜園やベランダ栽培では、支柱の種類や高さが仕上がりに直結します。
支柱の種類と特徴
ダイソーで取り扱っている支柱には、いくつかの種類があります。それぞれの特性を理解した上で選ぶと、ネット設置がよりスムーズに進みます。
| 支柱の種類 | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 樹脂コーティング支柱 | 軽くてサビにくい | ベランダやプランター用 |
| スチール製支柱 | 強度が高く、安定感がある | 地植えや風の強い場所 |
| フレームタイプ | 組み立て式で大きく展開可能 | 広い畑や本格的なガーデニング |
適切な高さの目安
植物の成長や設置環境に合わせて、支柱の高さを選びましょう。防虫ネットのサイズともバランスを取る必要があります。
-
草丈30〜50cm:60〜90cmの支柱
-
草丈80〜120cm:120〜150cmの支柱
-
室外機や物置などへの設置:ネットの幅+30cmを目安に
設置の工夫で安定性アップ
土が柔らかい場所では、支柱がぐらつくこともあります。このような場合には、支柱を深く差し込んだり、複数本を組み合わせて枠を作るなどの工夫が効果的です。また、結束バンドやゴムひもを使うとネットのズレ防止にもつながります。
防虫ネットの貼り方のポイント

防虫ネットを効果的に使うには、正しい貼り方を理解しておくことが重要です。貼り方次第で、虫の侵入を防げるかどうかが大きく変わってきます。
ピンと張るのが基本
ネットは、たるみのない状態で設置するのが基本です。たるんだネットでは、隙間ができてしまい、そこから虫が入り込んでしまいます。支柱やクリップを活用し、ネット全体を均一に張りましょう。
-
支柱の数は最低でも四隅に1本ずつ
-
風が強い地域では、補強用のロープを使用
-
重ね部分には洗濯ばさみやネット用クリップを使う
土や床との隙間をふさぐ
ネットの下部に隙間ができてしまうと、地面から這い上がってくる虫の侵入を許してしまいます。これを防ぐため、ネットの端を土に埋める、またはレンガなどの重りで押さえることが大切です。
ファスナーや開閉口の位置にも注意
日々の水やりや作業のしやすさを考えると、ネットには一部開閉できる部分を作っておくと便利です。ただし、その部分に隙間ができないよう、ファスナーやマジックテープでしっかりと閉じられるように工夫しましょう。
ダイソーとセリアと比較
100円ショップで購入できる防虫ネットですが、店舗によってサイズや使い勝手が異なります。ここでは、ダイソーとセリアの防虫ネットを比較し、選び方の参考になるようまとめました。
サイズや形状のラインナップ
両店舗ともに多様な商品を展開していますが、微妙にラインナップが異なります。以下に主要な違いをまとめました。
| 項目 | ダイソー | セリア |
|---|---|---|
| サイズ展開 | 90×180cm、120×200cmなど多様 | 小〜中型中心 |
| ネットの形状 | 網戸用・袋型・ロール型など豊富 | 袋型が中心 |
| カラー | ホワイト、グレーなど | ホワイトが中心 |
丈夫さと素材の違い
どちらもポリエステル製が多いですが、編みの細かさや耐久性に差があります。ダイソーの方が厚手でしっかりした作りのものが多く、屋外設置に向いています。セリアは軽くて扱いやすいため、室内用や小型プランターに最適です。
価格とコスパ
いずれも100円で購入可能ですが、同じ価格でもサイズが大きめのダイソーのほうがコスパは高めです。一方、セリアはデザインがシンプルでインテリアにもなじみやすい点が好まれています。


防虫ネット ダイソーの特徴と使い方まとめ
-
害虫対策として家庭菜園に最適なアイテム
-
ダイソーでは複数のサイズ・形状のネットを取り扱っている
-
主にポリエステル素材で耐久性に優れている
-
白・黒・グレーなど色によって用途が異なる
-
防虫だけでなく日よけや葉焼け防止にも使える
-
約2~3年の耐用年数が目安とされている
-
水通しが良く、基本的に外さずに水やり可能
-
支柱と合わせて使用することで効果を最大化できる
-
網戸の補修にも一時的に活用できる
-
室外機に使用することでゴミや虫の侵入を防げる
-
ファスナー付きネットを選ぶと作業効率が良くなる
-
設置時はネットをピンと張って隙間を防ぐのが基本
-
売り切れ時はセリアやキャンドゥも選択肢になる
-
サイズ選びは植物や設置場所に合わせて柔軟に対応する
-
セリアと比べてダイソーは大型サイズや屋外用が豊富