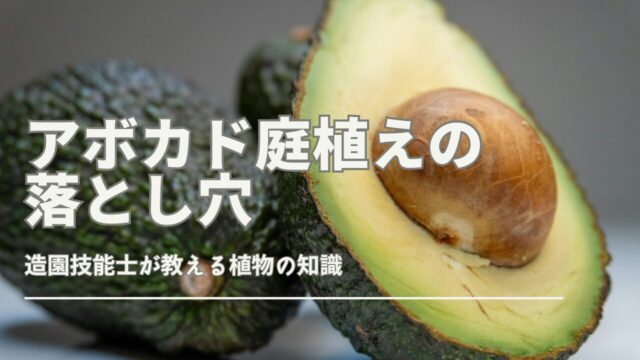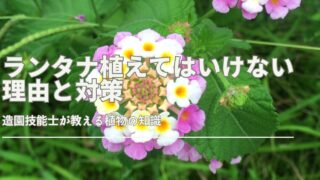ミョウガ植えてはいけない?連作障害を防ぐ栽培のポイント

ミョウガは家庭菜園でも育てやすい人気の植物ですが、「ミョウガ植えてはいけない」といった疑問を持つ人も少なくありません。実際、ミョウガを植えるとどうなるのか、広がるリスクや適切な栽培環境を知らずに育てると、思わぬトラブルにつながることがあります。
例えば、ミョウガは地下茎で増えるため、植える場所はどこがいいですか?と考えた際に、適切な環境を選ばないと周囲に広がりすぎてしまう可能性があります。また、連作障害がありますか?という点についても、同じ場所で育て続けると土壌の栄養バランスが崩れ、生育が悪くなることがあるため注意が必要です。
さらに、ミョウガの成長を促すには芽が出る時期は?という発芽のタイミングを把握し、適切な時期に植え付けを行うことが重要です。加えて、健康な株を維持するには、茎はいつ切るか?という管理方法も知っておく必要があります。
本記事では、これらの疑問を解決しながら、ミョウガの正しい育て方や注意点について詳しく解説します。ミョウガを栽培する際のリスクやポイントを理解し、家庭菜園を成功させるためのヒントを得てください。
- ミョウガを植えることで広がるリスクや管理の重要性を理解できる
- 適切な栽培環境や植える場所の選び方を知ることができる
- 連作障害や土壌の影響について学び、適切な対策を取れるようになる
- 芽が出る時期や茎の管理方法を知り、健康に育てるコツを理解できる
吉田宗弘(関西大学化学生命工学部栄養化学研究室)

ミョウガ植えてはいけない?栽培前に知るべきこと

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 名称 | ミョウガ(茗荷) |
| 学名 | Zingiber mioga |
| 特徴 | ショウガ科の多年草で、地下茎から花芽を形成する |
| 分布 | 日本を含む東アジア原産 |
| 食用部分 | 花穂(花みょうが)および若芽 |
| 栽培環境 | 半日陰で湿度の高い場所を好む |
| 注意点 | 地下茎が広がりやすく、管理が必要 |


ミョウガを植えるとどうなる?広がるリスクとは
ミョウガは比較的育てやすい植物だが、一度植えると想像以上に広がる特性がある。適切な管理をしないと、庭の他の植物の生育に影響を与えたり、望まない場所まで拡大することがある。ここでは、ミョウガを植えた際の広がるリスクについて解説する。
地下茎が広がりすぎる問題
ミョウガは地下茎で増殖するため、植えっぱなしにするとどんどん広がる。特に地植えの場合、意図しない場所まで繁殖することがあり、他の植物の生育を妨げることがある。
対策:
- 植える場所を限定する:畑や庭の一部に区画を作る
- プランター栽培を選ぶ:地下茎の広がりを防ぐ
- 防根シートを利用:地植えでも広がりすぎを防ぐ
他の植物との共存が難しい
ミョウガが広がると、他の植物と栄養やスペースを奪い合うことになる。特に根の張り方が強く、狭い範囲での共存が難しいため、混植には注意が必要だ。
影響を受けやすい植物:
- ほうれん草やレタスなど根が浅い野菜
- 栄養を多く必要とする野菜(ナスやトマトなど)
- ミョウガと同じ地下茎で増える植物(ショウガなど)
収穫が増えすぎることも
ミョウガは適切な環境で育つと、毎年収穫が可能になる。ただし、広がりすぎると、管理しきれないほど増えてしまうこともある。
対策:
- 間引きを行う:一定の間隔で地下茎を整理する
- 株分けを定期的に実施:2〜3年ごとに植え替える
- 栽培スペースをコントロール:増えすぎる前に適切な範囲を決める
ミョウガは管理を怠ると広がりすぎてしまうが、対策を講じれば適度に栽培できる。地下茎の増殖を抑えながら、長期間楽しめる環境を整えることが大切だ。
植える場所はどこがいいですか?適切な環境

ミョウガは育てやすい植物だが、適切な環境を選ばないと成長が悪くなり、収穫量も減少する。ここでは、ミョウガに最適な植え場所と環境のポイントを解説する。
日陰と半日陰がベスト
ミョウガは強い直射日光を苦手とし、半日陰の環境を好む。特に夏場の日差しが強い地域では、日陰に植えることでストレスなく育つ。
適した場所:
- 建物の北側や木の下:強い日差しを避けられる
- フェンス沿い:適度な日陰が確保できる
- 畑や庭の東側:朝日が当たり、午後は陰になる場所が理想的
水はけと適度な湿度が必要
ミョウガは湿気を好むが、過湿には弱い。水はけの悪い場所では根腐れを起こすことがあるため、適度な水はけを確保することが重要だ。
| 環境 | 適した条件 | 避けるべき条件 |
|---|---|---|
| 土壌 | 水はけがよく、腐葉土を含む肥沃な土 | 砂地や粘土質の土壌 |
| 湿度 | 適度な湿り気がある | 乾燥しすぎ・水浸し |
| 水やり | 乾燥しすぎないよう定期的に行う | 過剰な水やり |
地植えとプランターの選び方
ミョウガは地植えでもプランターでも栽培できるが、それぞれの環境で特徴が異なる。
地植えの特徴:
- メリット:管理が楽で収穫量が多い
- デメリット:地下茎が広がりやすい
プランター栽培の特徴:
- メリット:管理しやすく、広がりを抑えられる
- デメリット:乾燥しやすく、頻繁な水やりが必要
風通しの良さも重要
湿気がこもると病害虫の発生リスクが高まるため、風通しのよい環境を選ぶことも大切だ。特にプランター栽培の場合、風が通る場所に置くことで病害虫のリスクを減らせる。
適切な環境を選べば、ミョウガは手間をかけずに育てることができる。半日陰で水はけのよい場所を選び、栽培方法に合った管理を行おう。
連作障害がありますか?土壌の影響

ミョウガは連作に弱い植物の一つであり、同じ場所で育て続けると生育不良や病害のリスクが高まる。ここでは、連作障害の原因や対策について詳しく解説する。
連作障害の原因と影響
ミョウガを同じ場所で栽培し続けると、以下のような問題が発生する可能性がある。
| 原因 | 影響 |
|---|---|
| 土壌の栄養不足 | 生育不良、収穫量の減少 |
| 病原菌の蓄積 | 根腐れや病気の発生 |
| 土壌の硬化 | 水はけの悪化、根の成長阻害 |
特にミョウガは地下茎で育つため、土壌の栄養を大量に消費し、連作障害が起こりやすい。
連作障害を防ぐための対策
連作障害を防ぐためには、以下の方法を取り入れることが効果的だ。
- 栽培場所のローテーション:2〜3年ごとに植える場所を変える
- 土壌改良:腐葉土や堆肥を混ぜ、土の栄養を回復させる
- マルチング:敷き藁などで土の乾燥を防ぎ、微生物の働きを促す
- 休耕期間を設ける:数年間ミョウガを育てた場所は、一度休ませる
特に、収穫量の減少や葉の色が薄くなるなどの症状が見られたら、植え替えや土壌改良のタイミングと考えよう。
プランター栽培の対策
プランターで栽培する場合は、毎年新しい土に入れ替えることで連作障害を防ぐことができる。また、排水性の良い土を選ぶことで根腐れのリスクも軽減できる。
ミョウガの健康な生育を維持するためには、土壌の管理が重要だ。適切な対策を講じて、長期間の収穫を楽しもう。
芽が出る時期は?発芽のタイミング
ミョウガの発芽時期は気温や栽培環境によって異なるが、適切な管理をすれば安定した収穫が期待できる。ここでは、ミョウガの発芽時期と発芽を促すポイントについて解説する。
ミョウガの発芽時期の目安
ミョウガは春から初夏(4月〜6月)にかけて発芽する。地域によっても異なるが、一般的な発芽のタイミングは以下の通り。
| 地域 | 発芽時期の目安 | 平均気温 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 5月中旬〜6月 | 15℃〜20℃ |
| 関東・中部 | 4月下旬〜5月中旬 | 18℃〜23℃ |
| 関西・九州 | 4月中旬〜5月 | 20℃以上 |
ミョウガは気温が15℃以上になると地中から芽を出し始める。寒冷地では発芽が遅れやすいため、育苗やマルチングを活用するのも有効だ。
発芽を促すための管理方法
発芽をスムーズにするためには、以下のポイントに注意しよう。
- 土を湿らせる:乾燥すると発芽しにくくなるため、水やりを適度に行う
- 適度な日陰を確保:直射日光を避けることで、発芽後の生育が安定する
- 地温を上げる工夫:寒冷地では黒マルチや不織布を使って地温を確保する
特に、春先の寒暖差が激しい時期は発芽が遅れることもあるため、環境に合わせた調整が必要だ。
発芽後の管理ポイント
ミョウガが発芽した後は、以下の管理を徹底することで健康な株に育つ。
- 強い直射日光を避ける:日陰を好むため、適度な遮光が必要
- 適度な追肥を行う:発芽後に肥料を与えると成長が促進される
- 風通しを良くする:湿気がこもると病害虫が発生しやすいため注意
ミョウガの発芽時期を見極め、適切な管理を行うことで、元気な株を育てることができる。春の気温に注意しながら、栽培環境を整えていこう。
茎はいつ切るか?適切な管理方法

ミョウガの茎は適切なタイミングで切ることで、株の健康を保ち、翌年の収穫量を増やすことができる。ここでは、茎を切る適切な時期や方法について解説する。
茎を切る最適なタイミング
ミョウガの茎を切る時期は、生育状況や気候によって異なるが、一般的には収穫後の秋~冬が最適だ。
| 時期 | 管理の目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 収穫後(9月~10月) | 株の老化防止、病害虫対策 | 収穫が終わった茎を根元から切る |
| 冬(12月~2月) | 翌年の成長促進 | 地下茎を守るため、完全に枯れるまで待つ |
茎を切る理由とその効果
ミョウガの茎は収穫後も成長を続けるが、そのまま放置すると株が過密になり、翌年の発育に悪影響を及ぼす。適切に管理することで、以下のようなメリットが得られる。
- 株の栄養を温存できる:枯れた茎を除去することで、地下茎に養分が行き渡る
- 病害虫の予防:腐った茎が病気の原因となるため、早めに処理する
- 新しい芽の成長を促進:不要な茎を切ることで、翌年の発芽がスムーズになる
正しい茎の切り方
ミョウガの茎を切る際は、以下の方法を守ることで、株への負担を減らすことができる。
-
収穫が終わった茎を根元からカットする
- 花が咲き終わった茎は、そのまま枯れるため、根元から切る
- 切る際は、ハサミやナイフを使用し、傷口を綺麗にする
-
完全に枯れた茎は冬に除去する
- 冬の間に完全に枯れた茎を取り除くことで、新しい芽の発芽を助ける
- 寒冷地では、地面に残った茎が霜よけの役割を果たすため、一部を残すのも良い
-
切った後の管理も重要
- 土をならして、水はけを良くする
- 必要に応じて、腐葉土や堆肥を混ぜ、栄養補給を行う
ミョウガの健康な成長を維持するためには、適切な時期に茎を切り、土壌を整えることが重要だ。収穫後や冬の管理を徹底し、翌年の収穫に備えよう。
ミョウガ植えてはいけない?誤解と正しい育て方



みょうがは連作できますか?植え替えの必要性
みょうがは多年草のため、一度植えると数年間は収穫が可能です。しかし、同じ場所で何年も育て続けると、土の栄養が偏り、生育が悪くなる可能性があります。このため、定期的な植え替えが推奨されます。
みょうがの連作は避けるべき?
みょうがは連作に弱い植物です。連作を続けると、土壌の養分が不足し、収穫量が減少するだけでなく、品質の低下を招くことがあります。また、病害虫のリスクも高まるため、数年ごとに植え替えるのが理想的です。
どのくらいの頻度で植え替えるべき?
みょうがの植え替え頻度は 2~3年に1回 が目安です。特に、以下のような症状が見られたら、植え替えのタイミングと考えましょう。
| 植え替えが必要なサイン | 説明 |
|---|---|
| 収穫量の減少 | 以前より花芽が少なくなる、育ちが遅くなる |
| 茎や葉の密集 | 地下茎が広がりすぎて、株が過密になる |
| 土の劣化 | 土が固くなり、水はけが悪くなる |
連作を避けるための対策
みょうがの連作を避けるためには、栽培場所のローテーションや土壌改良が有効です。
- 栽培場所の変更:2~3年ごとに新しい土で育てる
- 土壌改良:堆肥や腐葉土を混ぜて栄養を補う
- プランター栽培の場合:古い土は新しい土と入れ替える
このような工夫を取り入れることで、みょうがを長期間健康に育てることができます。
植え替え時期は?株分けと植え替え方法

みょうがの植え替えは、新しい環境に適応しやすい時期に行うことが重要です。適切なタイミングで株分けや土の入れ替えを行うことで、翌年以降も健康なみょうがを育てられます。
みょうがの植え替えに最適な時期
みょうがの植え替えや株分けは、**休眠期の終わり(2~3月)**が適しています。この時期に植え替えることで、新しい芽がスムーズに成長できます。
| 地域 | 植え替え適期 |
|---|---|
| 寒冷地 | 4月 |
| 中間地 | 3月中旬~4月中旬 |
| 暖地 | 2月中旬~3月 |
株分けの方法
みょうがは地下茎(根株)を分けることで増やすことができます。株分けをすることで、栄養が行き渡りやすくなり、収穫量の増加が期待できます。
株分けの手順
- 地下茎を掘り出す:スコップなどを使い、傷つけないように注意しながら掘り起こす
- 不要な部分を取り除く:古い根や細い部分、傷んだ根をカットする
- 適切な大きさに分ける:1つの株に2~4つの芽がつくように切り分ける
- 新しい場所に植え付ける:土をほぐし、十分に湿らせた状態で植える
植え替え後の管理
植え替え直後は、根が安定するまでしっかりと水を与えましょう。また、日当たりの強い場所では遮光ネットを利用すると、乾燥を防ぐことができます。
ポイント
- 植え替え後は水やりを忘れずに
- 肥料は1か月後から与える
- 初年度の収穫は控えめにして、株を育てることを優先
このように適切な時期に植え替えを行うことで、みょうがの生育を安定させ、長く収穫を楽しむことができます。
みょうがの栽培方法は?プランターと地植えの違い
みょうがは比較的育てやすい野菜ですが、栽培方法によって管理の仕方が異なります。特にプランター栽培と地植え栽培では、メリット・デメリットがあるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
プランター栽培の特徴
メリット
- スペースを選ばず育てられる(ベランダや庭の片隅でも可能)
- 土の管理がしやすい(連作障害を防ぎやすい)
- 地下茎の広がりを抑えられる
デメリット
- 乾燥しやすい(水やりが欠かせない)
- 収穫量が少なくなる可能性(地植えに比べて生育スペースが狭いため)
- 定期的な植え替えが必要(土の劣化が早い)
プランターの選び方
みょうがは地下茎が広がる植物なので、深さ30cm以上のプランターを選ぶのがポイントです。幅も60cm以上あると、株が適度に成長しやすくなります。
地植え栽培の特徴
メリット
- 収穫量が多くなる(根が自由に広がりやすい)
- 手間が少ない(水やりの頻度が少なくて済む)
- 毎年の植え替えが不要(3〜4年は同じ場所で栽培可能)
デメリット
- 地下茎が広がりすぎる(他の植物の生育を妨げることがある)
- 土の管理が必要(連作障害を防ぐために定期的な土壌改良が必要)
- 場所を取る(プランターに比べて広いスペースが必要)
プランター栽培と地植え栽培の比較
| 栽培方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| プランター | 場所を選ばない、土の管理がしやすい | 乾燥しやすい、収穫量が少ない |
| 地植え | 収穫量が多い、手間が少ない | 地下茎が広がる、土の管理が必要 |
どちらの方法にも利点があるため、自分の環境に合った方法を選ぶことが大切です。プランターは管理がしやすく、地植えは収穫量が多いという特徴を考慮して、適切な方法でみょうがを育てましょう。
何回収穫できますか?収穫のタイミング

みょうがは多年草のため、一度植えると毎年収穫することができます。しかし、収穫の回数や時期を誤ると、品質が落ちたり、収穫量が減少することがあるため、適切な管理が必要です。
みょうがの収穫できる回数
みょうがの収穫回数は、生育環境と栽培方法によって異なります。
| 栽培方法 | 収穫回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 地植え | 3〜4年継続可能 | その後は植え替えが必要 |
| プランター | 2〜3年継続可能 | 土の劣化が早く、植え替えが必要 |
また、一つの株から年間2〜3回収穫できることもありますが、基本的には収穫期に一斉に収穫するスタイルが一般的です。
収穫のタイミング
みょうがは、地下茎から直接花芽(つぼみ)をつけます。このつぼみが開花する前に収穫するのがベストです。
収穫時期の目安
- 夏みょうが:6月〜8月
- 秋みょうが:9月〜10月
収穫する際のポイントは、つぼみが地表に出てきたタイミングで行うことです。開花してしまうと、食感や風味が落ちるため、つぼみが締まっているうちに収穫しましょう。
収穫の方法
- つぼみの根元を確認する:土から顔を出している部分を見つける
- 軽く土を掘る:手やスコップを使ってつぼみを傷つけないようにする
- ハサミや手で摘み取る:根元からねじるようにして収穫
注意点
- 収穫後はなるべく早く食べる(新鮮なうちが香りが強い)
- 収穫適期を逃すと、花が咲いて品質が低下する
- 収穫後は土をならして、次の生育の準備をする
みょうがの収穫は、植え付け1年目から可能ですが、本格的な収穫は2年目以降になります。毎年の収穫を楽しむために、定期的な植え替えや土壌改良を行うことが大切です。
花の咲いたミョウガは食べられる?食用の可否
ミョウガは一般的につぼみの状態で収穫され、食用として利用されます。しかし、収穫が遅れて花が咲いてしまった場合でも、食べることは可能です。ただし、食感や風味が変化するため、調理方法を工夫する必要があります。
花が咲いたミョウガの特徴
花の咲いたミョウガは、通常のつぼみよりも水分が抜けやすく、柔らかくなる傾向があります。また、以下のような変化が見られます。
| 状態 | 食感 | 風味 |
|---|---|---|
| つぼみ(収穫適期) | シャキシャキ | 独特の香りが強い |
| 開花後 | 柔らかい | 香りが弱くなる |
このため、食感を活かした料理ではなく、加熱調理や刻んで使用するのが適しています。
花が咲いたミョウガの食べ方
-
花びらも食べられる
花びらは繊細でほのかな香りがあり、料理の彩りとして活用できます。例えば、酢漬けや和え物に加えると見た目が華やかになります。 -
食感が硬い場合は加熱調理
つぼみよりも水分が少なく、筋張ることがあるため、天ぷらや炒め物にすることで食感を改善できます。 -
花が完全に咲いてしまった場合は観賞用に
花が咲ききると風味が落ち、硬くなるため、食用には適さなくなることがあります。その場合は観賞用として楽しむのも良いでしょう。
花が咲いてしまったからといって、必ずしも廃棄する必要はありません。適切な調理法を選ぶことで、最後まで美味しく味わうことができます。
生で食べても大丈夫ですか?安全な食べ方

ミョウガは、生で食べることができる野菜です。ただし、安全に食べるためには正しい下処理と食べ方を知っておくことが大切です。
生食する際の注意点
-
しっかり洗うことが重要
ミョウガの表面には、土や細かい汚れが付着していることがあります。特に露地栽培のものは虫が付いている可能性もあるため、流水でしっかり洗いましょう。 -
アク抜きをすると食べやすい
ミョウガには独特の苦味(アク)があるため、アク抜きをすることで食べやすくなります。
ミョウガのアク抜き方法
| 方法 | 手順 |
|---|---|
| 水にさらす | 切ったミョウガを冷水に30秒ほどさらし、水気をしっかり切る |
| 熱湯をかける | さっと熱湯をかけてから冷水にとると、アクが抜ける |
| 塩もみ | 薄切りにして軽く塩もみし、しばらく置いた後に水で洗い流す |
生食におすすめの食べ方
- 薬味として:冷奴やそうめん、味噌汁のトッピングに
- サラダに混ぜる:刻んでドレッシングと和える
- 甘酢漬けにする:ピクルスのようにして保存も可能
また、食べる際には食べ過ぎに注意が必要です。ミョウガには体を冷やす作用があるため、大量に摂取すると胃腸が冷えて不調を起こすこともあります。
適量を守りながら、さっぱりとした風味を楽しみましょう。
ミョウガは何年くらい生きますか?栽培期間の目安
ミョウガは多年草であり、一度植えれば数年間にわたって収穫が可能です。ただし、適切な管理を行わなければ、収穫量が減少することがあります。ここでは、ミョウガの寿命や栽培期間の目安について詳しく解説します。
ミョウガの栽培期間と寿命
ミョウガの地下茎は適切な管理をすれば5年以上生きることもありますが、収穫量のピークは3~4年程度です。そのため、数年ごとに植え替えを行うことで、長く健康な状態を保つことができます。
| 栽培年数 | 状態 | 収穫量 |
|---|---|---|
| 1年目 | 株が成長し、収穫は少なめ | やや少なめ |
| 2~3年目 | 株が充実し、最も収穫量が多い | 多い |
| 4~5年目 | 根茎が混み合い、収穫量が減少 | 減少傾向 |
| 6年以上 | 栄養不足で株が弱る | ほとんど収穫できない |
このように、3~4年目が最も収穫に適した時期ですが、それ以降は地下茎が過密になり、生育が悪くなるため、適切な管理が必要です。
長く収穫を続けるためのポイント
-
2~3年ごとの植え替えを行う
地下茎が増えすぎると栄養が分散し、ミョウガの生育が悪くなります。そのため、2~3年ごとに掘り起こし、株分けや植え替えを行うことが推奨されます。 -
適切な施肥を行う
ミョウガは肥料を適度に与えることで健康な株を維持できます。特に、**収穫後の「お礼肥」**を施すことで、翌年の生育を助けることが可能です。 -
環境を整える
乾燥や過度な直射日光はミョウガの成長を妨げる要因となります。特に夏場は、敷きわらやマルチングを活用し、適度な湿度を維持することが重要です。
栽培期間を延ばすための植え替え方法
ミョウガは適切に管理すれば5年以上生育することもありますが、連作を嫌う性質があるため、同じ場所での栽培を続けると収穫量が減少します。長期間収穫を楽しむためには、以下の方法で植え替えを行いましょう。
-
地下茎を掘り起こす
冬から春(2~3月頃)にかけて、株を掘り上げます。 -
古い根を整理する
細くなった根や傷んだ部分を取り除き、健康な地下茎だけを残します。 -
新しい用土に植え替える
連作障害を避けるため、新しい土に植え付けるか、別の場所に植え替えるのが理想です。
このような管理を行うことで、ミョウガの栽培期間を延ばし、安定した収穫を続けることができます。
ミョウガは多年草であり、5年以上生きることができますが、収穫のピークは3~4年程度です。植えっぱなしにすると収穫量が減少するため、2~3年ごとに植え替えや株分けを行うことで、長期間栽培を楽しむことができます。適切な管理を行いながら、美味しいミョウガを育てましょう。


ミョウガ植えてはいけない?正しい育て方と注意点
- ミョウガは地下茎が広がりやすく、放置すると庭全体に広がる
- 連作障害が起こるため、同じ場所での長期栽培は避けるべき
- 収穫量を維持するには2〜3年ごとに植え替えが必要
- 日陰を好むが、極端に暗い場所では生育が悪くなる
- 土壌が固くなると成長が鈍るため、定期的な土壌改良が必要
- プランター栽培は地下茎の広がりを抑えやすく、管理しやすい
- 地植えは収穫量が多いが、適切な場所を選ばないと他の植物に影響を与える
- ミョウガの発芽時期は春(4〜5月)、収穫は夏から秋
- 収穫適期を逃すと花が咲き、食感や風味が落ちる
- 花が咲いたミョウガも食べられるが、加熱調理が適している
- 生で食べられるが、しっかり洗いアク抜きをすると食べやすい
- 5年以上生育可能だが、3〜4年目を過ぎると収穫量が減少
- 過密になると茎や葉が茂りすぎ、花芽の発育が悪くなる
- 乾燥や直射日光が苦手で、適度な湿度を保つことが重要
- 植え替え後は1か月程度、株を安定させるために収穫を控える
参考文献・出典(ミョウガ〈Zingiber mioga〉の性質・栽培・管理)
Kew Science|Plants of the World Online:Zingiber mioga(学名・原産域・分類)
Royal Horticultural Society(RHS)|Zingiber mioga(性質・栽培特性・草丈)
NC State Extension|Zingiber mioga(半日陰・用土・2–5年での株の広がり)
高知県「こうち農業ネット」|家庭菜園(ミョウガ)(品種・植付・施肥・年間管理)
農研機構 資料|夏秋ミョウガの安定生産技術(3–4年で過密→間引き・更新の必要)
福岡県農林業総合試験場|ミョウガ根茎の休眠打破と早出し技術(定植・被覆・加温)
福岡県農林業総合試験場|ミョウガの品種比較と温度管理(収量・品質の指標)
岩手県 農業改良資料|夏ミョウガの早出し技術(被覆・保温・時期調整)
JAグループ(佐賀)|家庭菜園:ミョウガ(連作を避け更新・用土のポイント)
マイナビ農業|みょうがの育て方(半日陰・植替え時期・株分け手順)
家庭菜園ガイド|みょうが栽培カレンダー(植付・発芽・収穫の時期目安)
農研機構 研究成果情報|施設遅出しミョウガ(定植時期・電照による出荷時期調整)