ブーゲンビリア花が咲かない人必見の肥料と剪定のコツ

ブーゲンビリアは、その鮮やかな色合いで庭やベランダを彩る人気の植物ですが、「ブーゲンビリア花が咲かない」と悩む方も少なくありません。せっかく育てているのに、花が見られずに葉っぱばかりが茂ってしまうと、管理方法に不安を感じるものです。この記事では、ブーゲンビリアの花が咲かない原因は?という疑問に答えながら、葉っぱばかりになる理由や新芽が出ないときの対処法についても詳しく解説していきます。
また、冬に葉が落ちるのは普通?という季節ごとの疑問や、健康な株に育てるための剪定のタイミングと注意点についても取り上げます。さらに、ブーゲンビリアを上手に咲かせるためには、開花時期を理解しようとする姿勢がとても重要です。開花の条件をしっかり押さえた上で、日常の管理を見直してみましょう。
-
花が咲かない主な原因とその対策方法
-
肥料・剪定・日照など育て方の改善ポイント
-
葉ばかり茂る理由と栄養バランスの見直し方
-
季節ごとの管理と開花時期に応じたケア方法
Botanical Society of America – 植物科学に関する知見
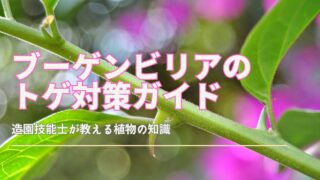
ブーゲンビリア花が咲かない原因を知る

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | ブーゲンビリア(筏葛、九重葛) |
| 学名 | Bougainvillea |
| 特徴 | 鮮やかな色の苞が特徴的なつる性低木。実際の花は小さく、苞の中心に位置する |
| 分布 | 中南米原産。日本では温暖な地域で栽培される |
| 開花時期 | 主に5月から10月。温室では周年開花も可能 |
| 栽培 | 日当たりと水はけの良い場所を好む。乾燥気味に育てると花付きが良くなる |
| 注意点 | 寒さに弱いため、冬季は室内で管理する。水の与えすぎに注意 |


ブーゲンビリアは1日6時間以上の直射日光が必要ですが、室内や日陰では難しい場合があります。そのような環境では、植物育成用のLEDライトが効果的です。特に、フルスペクトルのLEDライトは、光合成に必要な波長をカバーし、開花を促進します。タイマー機能付きのモデルを選べば、日照時間の管理も容易です。
ブーゲンビリアの花が咲かない原因は?
ブーゲンビリアがなかなか花をつけずに悩んでいる方は少なくありません。色鮮やかな花を咲かせるためには、植物の生育サイクルや管理方法を理解しておくことが重要です。ここでは、花が咲かない主な原因とその対処法を解説します。
日照不足による光合成の低下
ブーゲンビリアは熱帯性の植物で、1日に最低でも5〜6時間以上の直射日光が必要です。日照時間が足りないと、十分な光合成が行えず、花を咲かせるためのエネルギーが蓄積できません。
| 条件 | 花付きの影響 | 推奨環境 |
|---|---|---|
| 日照時間3時間以下 | 咲かない可能性大 | 屋内や日陰では不適 |
| 日照時間4〜5時間 | 咲くが花数が少ない | 半日陰は注意 |
| 日照時間6時間以上 | 花付きが良好 | ベランダや南向きが理想 |
肥料の与え方に偏りがある
窒素分が多い肥料を与えすぎると、葉や茎の成長が促進される一方で、花芽の形成が抑制されることがあります。花付きにはリン酸(P)が多く含まれる肥料が効果的です。
窒素分が多い肥料は葉や茎の成長を促進しますが、花芽の形成を抑制することがあります。ブーゲンビリアの開花には、リン酸が多く含まれる肥料が効果的です。例えば、花ごころ 超リンカリ肥料は、花付きに特化しています。緩効性の粒状タイプを選べば、長期間にわたり栄養を供給できます。
適切な剪定をしていない
ブーゲンビリアは剪定後に出る新芽に花芽がつきやすい性質があります。古い枝ばかりを残しておくと、新芽が出にくくなり、結果として花が咲かなくなります。剪定は開花後か春先に行うのが効果的です。
成長期と休眠期を誤認している
一般的にブーゲンビリアの開花時期は初夏から秋ですが、地域や気候により異なることもあります。冬場は休眠期に入るため、葉が落ちたり活動が鈍くなったりしても、すぐに枯れたと判断しないようにしましょう。
葉っぱばかりになる理由

花が咲かずに葉ばかりが茂っているブーゲンビリアは、一見健康そうに見えても、育て方に偏りがある場合が多いです。このような状態では、植物の栄養や光のバランスを見直すことが必要です。
肥料の栄養バランスが偏っている
葉が茂る一番の原因は、窒素分(N)が多い肥料を与えすぎていることです。窒素は葉や茎の成長に関わる成分であり、これが過剰だと花芽の形成が抑えられてしまいます。
| 肥料成分 | 主な役割 | 花付きへの影響 |
|---|---|---|
| 窒素(N) | 葉や茎の成長促進 | 過剰だと花が咲きにくい |
| リン酸(P) | 花や実の成長促進 | 花付きに必要 |
| カリ(K) | 根の成長・耐病性 | バランス維持に重要 |
剪定せずに古い枝が残っている
枝が込み入って風通しが悪いと、新芽が出づらくなり、葉は繁茂するが花芽がつかない状況になります。毎年適切に剪定を行い、新しい枝を育てることがポイントです。
水やりの頻度が多すぎる
ブーゲンビリアは乾燥に強く、やや乾かし気味に育てる方が花付きがよくなる傾向があります。常に土が湿っている状態では、葉ばかりが茂ってしまい、花がつきにくくなります。
室内や日陰で育てている
葉は日陰でもある程度育ちますが、花芽の形成には強い日差しが不可欠です。室内や北側のベランダなどでは、光量不足により花が咲かず、葉ばかりが成長してしまう原因となります。
新芽が出ないときの対処法
ブーゲンビリアの新芽がなかなか出ないと、「枯れてしまったのでは?」と不安になる方もいるでしょう。実は、いくつかの管理方法を見直すことで、新芽の発生を促すことが可能です。ここでは、新芽が出にくい原因とその解決策について解説します。
剪定のタイミングが遅れている
ブーゲンビリアは、剪定後の新芽に花芽がつきやすい性質があります。適切なタイミングで剪定を行わないと、新しい芽が出にくくなります。特に春〜初夏にかけて剪定すると、健康な芽が出やすくなります。
| 剪定の時期 | 新芽の出やすさ | 備考 |
|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 非常に良い | 生育開始と合う |
| 夏(6〜7月) | 良い | 花後の整枝に適す |
| 秋以降 | 出にくい | 休眠に入るため不向き |
栄養が不足している
新芽の発育には十分な栄養が必要です。長期間植え替えをしていない鉢や、肥料切れの状態では、新しい芽が育ちにくくなります。緩効性の元肥や、リン酸・カリを含む液肥を適切に与えるとよいでしょう。
根詰まりや過湿がある
鉢植えの場合、根が詰まると養分や水分の吸収が阻害され、芽の成長が鈍くなります。また、水はけの悪い環境や過湿状態でも根がダメージを受けやすく、新芽の成長に影響を及ぼします。1〜2年に1回は植え替えを行いましょう。
冬に葉が落ちるのは普通?
-640x360.webp) 画像出店:観葉植物のある暮らし
画像出店:観葉植物のある暮らし冬になるとブーゲンビリアの葉が落ちてしまうことがありますが、これは多くの場合、生理的な現象であり心配はいりません。どのような状況が正常で、どこからが異常なのかを整理しておくと安心です。
ブーゲンビリアは落葉することがある
ブーゲンビリアは常緑性に分類されますが、気温が10℃以下になると落葉することがよくあります。これは寒さから身を守るための自然な反応で、春になると再び葉が芽吹くので心配は不要です。
| 気温の目安 | 葉の状態 | 対処法 |
|---|---|---|
| 15℃以上 | 落葉しない | 通常の管理でOK |
| 10〜14℃ | 部分的に落葉 | 水やりを控えめに |
| 9℃以下 | 完全に落葉 | 室内または防寒対策が必要 |
室内越冬でも葉が落ちることがある
室内で管理していても、急激な温度変化や乾燥した空気により葉が落ちることがあります。暖房の風が直接当たる場所や、湿度の低い部屋では、落葉が起きやすいので注意が必要です。
葉が落ちたあとの対応
落葉した後は、水やりの回数を減らし、根腐れや過湿を避けて管理を続けることが重要です。春になれば新芽が自然と出てきますので、あわてて剪定をする必要はありません。目安としては、3月ごろから水やりを再開し、芽の動きを確認しましょう。
剪定のタイミングと注意点
ブーゲンビリアを健康に育て、花つきを良くするには、剪定のタイミングと方法がとても重要です。間違った時期に剪定すると、かえって花芽を減らしてしまう可能性もあります。ここでは、剪定の基本と注意点を整理して解説します。
ブーゲンビリアの剪定は、花付きに大きく影響します。適切な剪定を行うためには、切れ味の良い剪定用ハサミが必要です。特に、ステンレス製で錆びにくいハサミは、長期間使用できます。また、握りやすいグリップ付きのモデルを選べば、作業中の手の疲れも軽減されます。
剪定に適した時期は春と夏
ブーゲンビリアの剪定は、春(3〜5月)または初夏(6〜7月)が適期です。この時期は成長が活発で、新しい枝がどんどん伸びるため、剪定してもすぐに新芽が出てきます。
| 剪定時期 | 特徴 | 適した目的 |
|---|---|---|
| 3〜5月(春) | 成長開始期 | 枝数を増やして花芽を誘導 |
| 6〜7月(初夏) | 開花直後 | 形を整えて次の花に備える |
| 秋〜冬 | 成長停止期 | 剪定は避ける方がよい |
剪定のポイントは枝の位置と角度
太い枝を中心に、外向きの芽の上で切るのが基本です。こうすることで、枝が外に向かって広がり、風通しも良くなります。また、枝の分岐点より少し上を斜めに切ると、水分が溜まりにくく、病気予防にもなります。
切りすぎに注意!花芽まで落とす可能性
勢いよく刈り込むと、花芽がつくはずの枝を落としてしまうことがあります。特に夏以降の剪定では、先端についたつぼみを誤って切らないよう、枝の様子をよく観察してから作業しましょう。
開花時期を理解しよう

ブーゲンビリアの花を美しく咲かせるためには、いつ花が咲くのかを正しく知っておくことが大切です。開花のサイクルに合わせて手入れや環境を調整すれば、より長く、より鮮やかな花を楽しめます。
ブーゲンビリアの主な開花時期は春〜秋
ブーゲンビリアは暖かい気候を好み、一般的には4月〜11月ごろまで咲き続ける多年草です。特に日照時間が長く、乾燥している時期に多くの花を咲かせる性質があります。地域によって多少前後するため、自宅の気候に合った観察が大切です。
| 地域 | 開花のはじまり | 開花のピーク | 開花終了時期 |
|---|---|---|---|
| 関東・東北 | 5月中旬 | 6月〜9月 | 10月下旬 |
| 関西・九州 | 4月下旬 | 5月〜9月 | 11月上旬 |
| 沖縄など暖地 | 3月下旬 | 4月〜10月 | 11月下旬 |
短日植物だが「管理次第」で複数回開花も可能
ブーゲンビリアは短日植物に分類され、日照時間が短くなることで花芽を形成します。しかし、一定の条件がそろえば、年間で複数回咲かせることも可能です。日照・水やり・剪定のタイミングを意識すれば、開花をうまく誘導できます。
-
1回目:春先(3月〜5月)に開花
-
2回目:夏剪定後(7月〜9月)に再開花
-
3回目:気候が温暖なら11月頃まで花を維持可能
このように、剪定と乾燥気味の管理をセットで行うと、次の開花を促すことができます。
冬は休眠期に入るため開花しない
寒くなる12月〜2月は休眠期に入り、花は咲きません。この間は葉を落とし、枝だけの状態になることもありますが、枯れたわけではありません。春の再生に向けてしっかりと休ませてあげることが、次の花を美しく咲かせる準備になります。
ブーゲンビリア花が咲かないときの対策



ブーゲンビリア 花を咲かせる方法とは?
「つぼみすら付かない」「葉は元気なのに花が見られない」と感じる場合は、育て方に少し工夫が必要かもしれません。ブーゲンビリアに花を咲かせるには、環境・剪定・水やりの3つが鍵です。
日光をたっぷり与える
ブーゲンビリアは強い日差しを好みます。1日6時間以上の直射日光が必要です。光が足りないと花芽が形成されにくく、葉ばかりが繁ってしまいます。室内や半日陰ではなく、ベランダや庭の南向きでの管理が効果的です。
水やりは控えめが基本
開花を促すにはやや乾燥気味の管理が重要です。土が乾いてから2〜3日後に水を与えるペースが理想的で、過湿は根腐れや花付きの悪化につながります。特に花芽形成期(春〜初夏)には注意しましょう。
開花期を見越した剪定を行う
剪定はブーゲンビリアの花付きに直結します。開花後に伸びた枝を2〜3節残して切り戻すことで、新芽に花芽がつきやすくなります。切りすぎると花芽をつける節までなくなってしまうため、長さの調整も大切です。
花を咲かせる肥料|元肥には何がいい?

ブーゲンビリアの開花には肥料の種類と与え方が大きく影響します。過剰な栄養は葉ばかり育ち、肝心の花が咲きません。ここでは適切な「元肥」と「追肥」の選び方を整理します。
リン酸を多く含む肥料を選ぶ
花付きに効果的な成分はリン酸(P)です。葉や茎を伸ばす窒素(N)が多すぎると逆効果になるため、N-P-K比が低窒素・高リン酸のタイプが理想です。以下の表に、代表的な肥料の成分比較を示します。
| 肥料の種類 | N(窒素) | P(リン酸) | K(カリウム) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 草花用化成肥料 | 10 | 30 | 10 | 花付きに特化 |
| 一般的な園芸用肥料 | 20 | 20 | 20 | バランス型 |
| 葉物用肥料 | 30 | 10 | 10 | 葉が育ちやすく花付きには不向き |
元肥は春先に、控えめに与える
植え付け時や植え替え時には、鉢底や土全体にゆっくり効く緩効性肥料を混ぜておくのが効果的です。過剰な施肥はかえって逆効果になるため、説明書の量よりやや少なめに調整するのがポイントです。
追肥で開花をコントロールする
元肥だけでは開花をコントロールできないため、花芽がつき始める5月〜6月頃に液体肥料を週1回程度与えるのが望ましいです。水やりと兼ねることで肥料焼けのリスクも軽減できます。
日照時間と環境を見直すポイント
ブーゲンビリアの開花において「日照」は最も重要な条件の一つです。屋外で育てていても、光量や風通しが不十分だと、花が咲かない原因になります。今育てている環境を見直し、適した場所を選び直すことが開花への第一歩です。
日照は「直射日光6時間以上」が目安
ブーゲンビリアは日光を多く必要とする植物です。特に春から秋にかけては、1日6時間以上の直射日光が求められます。光が弱いと、光合成が不十分になり、花芽が形成されにくくなります。曇天や日陰が多いベランダでは開花しにくくなる傾向があります。
| 環境条件 | 日照時間 | 開花への影響 |
|---|---|---|
| 南向きの庭 | 6時間以上 | ◎ 開花しやすい |
| 東・西向きのベランダ | 3〜5時間 | △ 開花は条件次第 |
| 北向き・室内 | 2時間以下 | × 花が咲きにくい |
風通しと湿度も意識する
密閉されたベランダや、風の通らない場所では、湿気がこもりがちです。ブーゲンビリアは乾燥気味を好む性質があるため、風通しのよい環境に置くことで根腐れや病気のリスクも減ります。
屋外管理が難しいなら移動管理を検討
日照が足りない場合は、キャスター付きの鉢での管理をおすすめします。日中は日向に出し、夜間や雨天時は軒下に避難することで、光と風のバランスをとることができます。
水やりの頻度と量に注意しよう

ブーゲンビリアは乾燥に強い反面、過剰な水やりで花付きが悪くなる傾向があります。水やりの頻度やタイミングを見直すことで、植物の健康を守りつつ花芽の形成を促進できます。
ブーゲンビリアは乾燥気味に育てる方が花付きが良くなります。過湿を避けるためには、土壌の水分量を正確に把握することが重要です。土壌水分計を使用すれば、土の乾燥具合を簡単に確認でき、適切なタイミングでの水やりが可能になります。
土が乾いてから数日待って水やりする
基本のスタイルは「乾いてから数日後にたっぷり」です。毎日少しずつ与えるよりも、乾燥と潤いを繰り返す方が花芽がつきやすくなります。特に春~初夏はやや乾かし気味が理想です。
季節ごとの水やり目安を把握しよう
| 季節 | 水やり頻度(目安) | ポイント |
|---|---|---|
| 春〜初夏 | 3〜4日に1回 | 土が乾いてから2日ほどあける |
| 真夏 | 2〜3日に1回 | 朝か夕方の涼しい時間帯に |
| 秋 | 4〜5日に1回 | 気温低下に伴い水分を減らす |
| 冬 | 7〜10日に1回 | 休眠期。乾燥気味で越冬させる |
受け皿の水は必ず捨てる
根腐れを防ぐため、鉢の受け皿に溜まった水は都度捨てるようにしましょう。特に夏場は蒸れやすく、病気や害虫の温床にもなります。
鉢植えと地植えで違う管理方法
ブーゲンビリアは鉢植えと地植えで育て方に大きな違いが出ます。置き場所や水やり、冬越し対策など、環境に合わせて適切に管理することが、花を咲かせる上で重要なポイントになります。
鉢植えは移動ができる分、管理がしやすい
鉢植えの最大のメリットは「日照の確保がしやすいこと」です。日当たりの良い場所に自由に移動できるため、季節や天候に合わせて最適な環境を維持できます。また、冬場は室内に取り込んで越冬させることができ、寒さによるダメージを防げます。
地植えは成長が旺盛、剪定や冬対策が重要
地植えは根の張りがよく、成長スピードが早いため株が大きくなりやすい反面、剪定の手間が増えたり、冬の寒さ対策が必要になります。温暖な地域であれば地植えでも毎年よく咲きますが、寒冷地では霜害のリスクを考慮する必要があります。
植え方による管理の違いを表で確認
| 管理項目 | 鉢植え | 地植え |
|---|---|---|
| 日照調整 | 移動できる | 移動不可。設置場所が重要 |
| 水やり頻度 | 季節によって頻繁に調整が必要 | 土壌の保水力により間隔が長くなる |
| 冬の対策 | 屋内に移動できる | 寒冷地では防寒・霜除けが必須 |
| 剪定の必要性 | コンパクトに保ちやすい | 成長が早いため頻度が高い |
再び咲かせるための育て方のコツ

一度花が終わった後も、正しいケアをすれば再びブーゲンビリアを咲かせることができます。ポイントは「光・水・剪定・肥料」の4要素をバランスよく整えることです。
開花後は軽く剪定して次の花芽を促す
花が終わったら、枝先の5~10cmを軽く剪定しましょう。そうすることで、風通しがよくなり、新しい枝が伸びて花芽がつきやすくなります。古い枝を放置すると、栄養が分散してしまい次の花が咲きにくくなることがあります。
肥料はリン酸成分が多いタイプを選ぶ
花芽の形成にはリン酸が多めに含まれた肥料が適しています。窒素が多すぎると葉ばかり育ってしまうので、花専用の追肥を与えるのが効果的です。開花後1か月おきに与えると、次の開花サイクルが安定します。
| 肥料の種類 | 特徴 | おすすめタイミング |
|---|---|---|
| リン酸型(花用) | 花芽形成を促進 | 開花前後の追肥として |
| 窒素型(葉用) | 葉を増やすが、花芽には不向き | 育成初期に少量使用 |
| 緩効性化成肥料 | ゆっくり効き、安定した生育を支える | 春の元肥として適している |
水やりと日照を再チェックする
夏の高温期や梅雨時は、水の管理が特に重要です。乾きすぎず、湿りすぎずのバランスを保ちながら、日光はしっかり確保しましょう。環境が整えば、ブーゲンビリアは年に2〜3回開花することも珍しくありません。


ブーゲンビリア花が咲かないときの原因と対策のまとめ
-
日照時間が不足すると光合成が不十分で花芽がつかない
-
窒素分が多い肥料は葉ばかり繁らせて花が咲きにくくなる
-
剪定のタイミングが遅れると新芽が出ず花芽も形成されない
-
剪定しないと古い枝が残り、新芽の発生が抑えられる
-
水の与えすぎは根腐れや葉ばかりの成長を招く
-
冬の寒さで落葉しても休眠期であり枯れているわけではない
-
開花期に合わせた管理ができていないと花が咲かない
-
日光は1日6時間以上の直射日光が理想的
-
室内や北向きでは日照不足になりやすい
-
肥料はリン酸が多く含まれるタイプを選ぶべき
-
鉢植えは移動ができるため日照管理がしやすい
-
地植えは根が張るため成長が旺盛で剪定の頻度が高まる
-
根詰まりや植え替え不足は新芽の成長を妨げる
-
ブーゲンビリアは短日植物であり日照管理が開花に影響する
-
開花後に軽く剪定することで次の花芽がつきやすくなる















